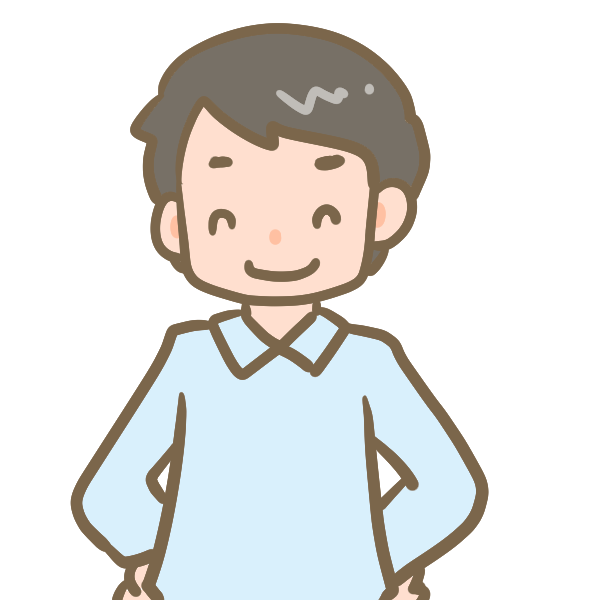現在相談中の方で、下記記事に該当する事案があります。その相談者に参考になる記事を公開すると先日約束しました。同様のことで悩まれている方にとっても参考になるはずなので、ぜひご覧になってください。
目次
傷病名が「頚椎捻挫(むちうち)」から「脊髄損傷」に変更
受傷当時の傷病名が「頚椎捻挫」あるいは「むち打ち症」だったものが、その後、「脊髄損傷」に変わることがあります。相談の中でも比較的目につきますね。いずれも重篤かつ多彩な症状なのですが、ひとつのタイプは、事故との因果関係が疑われているもの、もうひとつのタイプが、事故との因果関係が存在するとされたものの、後遺障害等級が14級どまりのものです。脊髄損傷なのにどうして14級なのかということです。
ご相談の内容は、前者は事故との因果関係を認めるにはどうしたらよいのか、後者は、上位後遺障害等級を獲得するためにはどうしたらよいのかというものです。脊髄損傷に関しては、以上の2つの論点以外に、脊髄損傷の存在自体を否定するもの、既往症による素因減額も論点になります。(「後遺障害等級認定と裁判実務」P239)。
脊髄損傷で後遺障害認定を獲得するために必要なこと
自賠責実務で脊髄損傷が存在すると言われるためには、損傷された脊髄レベルが特定できて、その診断根拠となる神経学的所見、すなわち知覚機能、運動機能、反射機能のいずれにも明確な異常所見がみられ、その具体的部位・領域・筋名・反射名などが明記されており、解剖学的な神経支配理論の観点から、これら神経学的所見の間で一致がみられ、かつ損傷レベルとの整合性もある場合です。
あるいは、画像所見で損傷された脊髄レベルの特定ができなかった場合でも、神経学的所見で脊髄損傷(麻痺)の発生・存在を説明できる場合だと言われています。
ところが、典型的な脊髄損傷の場合の症状・所見と、実際に問題になっている「脊髄損傷」との間に「ズレ」があることがある(前掲書P239)。たとえば、教科書的には脊髄損傷がある場合には、通常、四肢の腱反射が亢進するとありますが、実際は、亢進していないことも少なくありません。
この場合は、腱反射だけでなく病的反射や筋委縮などの有無を調べ、新たに画像検査や電気生理学的検査(筋電図・神経伝導速度検査・誘発電位検査など)を実施して、総合的な確定診断をするしかありません。
各種検査の「証明度」
損保業界に絶大な影響力を有する井上久drは、症状(主観的なもの)と所見(第三者がわかる客観的なもの)に2分類し、所見については、主観の入りやすいものからそうでないものにさらに3分類して、ランク付けをしています。「証明」を考える際に大変参考になると思われるので、当方で以下のようにまとめてみました。
純粋な自覚症状
痛み、しびれ、凝り、倦怠感、脱力感、冷感、火照り・・・
①主観を通した他覚所見
②主観も入り得る他覚所見
③客観的に証明される厳密な意味での他覚所見
以下、「㈡客観」に属する他覚所見についてのそれぞれの説明です。なお、医師は主観・客観を上記のように区分しますが、賠償分野では「㈠主観」+「㈡客観①」までが主観に属するとして、いわゆる「他覚的所見」について限定的な解釈をしています。医者の考える「他覚的所見」と、賠償分野の人が考える「他覚的所見」とは違うわけです。
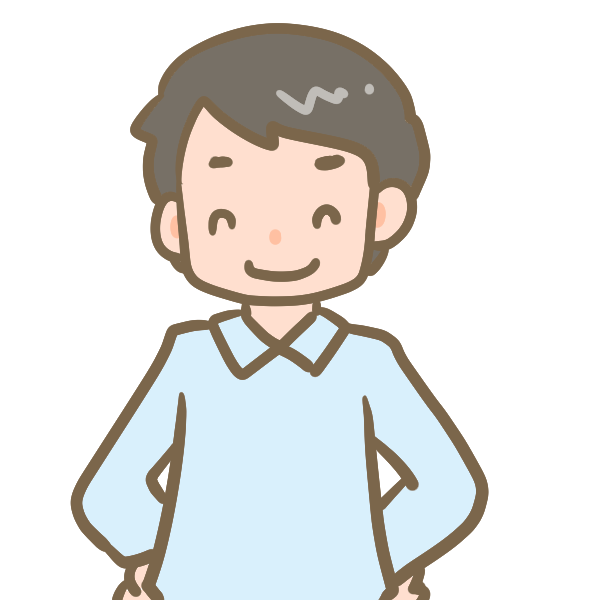
①患者の自覚的訴え・申告に基づき客観的に把握されるもので、心因性要因もしくは意図的要因が容易に入る可能性あり。例:圧痛、疼痛性可動域制限、握力、スパーリングテストなどの神経根圧迫徴候、ラセーグ・SLRテストなどの神経根牽引徴候・・・
②知覚・運動・反射など総合的所見や、場合により各種画像検査、電気生理学的検査、専門的特殊検査などによる裏付けが必要になるもの。例:知覚鈍麻・脱失、筋力低下、手指巧緻運動障害、排尿障害、性機能障害、歩行障害・歩容異常・・・
③客観的に証明される厳密な意味での他覚所見。例:出血、皮下出血、腫脹、浮腫、皮膚変色、皮膚瘢痕、発汗異常、脱毛、筋硬結・過緊張、筋委縮、反射異常、変形、血液検査所見、画像検査所見、電気生理学的所見(筋電図、神経伝導速度、各種誘発電位検査・・・)
傷病名が変わった理由
ところで、どうして傷病名が途中から変わったのでしょうか。このことで、事故との因果関係にかかわる論点が問題になることがあります。事故が軽微なため、そのような事故状況では脊髄損傷などという重篤な症状にならないだろうこと。こういう場合は、たいてい画像所見上もいわゆる他覚的所見がないことが多いため、事故との因果関係が否定されるケースです。
その理由について、これまで当方が経験したものや、医学書によって示された例をあげてみることにします。
原因別に分類すると、以上の7分類がだいたい可能かと思います。以下にそれを表にしてみました。
| 当初頚椎捻挫だったものが脊髄損傷に変わった原因 | ||
|---|---|---|
| 1 | 検査不足 | 当初、レントゲンの画像検査しか実施しておらず、後日、MRI検査をして脊髄損傷が判明した場合 |
| 2 | 初医の読影ミス | 不適切なレントゲン撮影・読影によって脊髄損傷であることを見逃した場合 |
| 3 | 他の外傷に気を奪われたこと | 重篤な合併症があったために、脊髄損傷があることを見逃した場合 |
| 4 | 当初の訴えが軽かったための診断ミス | 当初軽い訴えだったために、脊髄損傷があることを見逃した場合 |
| 5 | 既往障害との混同 | 脳由来の麻痺が既存としてあったために、脊髄損傷による症状を既存障害と、誤・判断した場合 |
| 6 | 肩外傷の合併 | ・・・による見逃しの場合 |
| 7 | 主治医の怠慢 | 主治医の単純ミス・注意不足による見逃しの場合 |
傷病名が頚椎捻挫から脊髄損傷に途中から変わったときに、そこにどういう理由があるのかを事前に知っておくと、医師面談の際の漏れが少なく、たいへん有効です。以下に具体例で考えてみます。
検査不足によるもの
当初X線検査のみ、その後症状が改善されないもしくは悪化したためMRI検査を実施した結果、脊髄損傷であるとの画像読影があったケース。これはよくあるケースです。
初医の画像誤読影によるもの

画像読影ができない私でもおかしいじゃないのかと思わせる事例。単純X線側面像。第6頚椎の前方脱臼の例ですが、前医の撮影したこの画像には肩に隠れているため、第6、第7頚椎がそもそも写っていません。この画像だけで骨傷なしと判断するのですから論外です。後医の撮影した画像では第6、第7頚椎も写っており、脱臼があることが分かります。
このような誤読影というか、手抜きが原因のものがあります。

また、第7頚椎/第1胸椎を中心とした高位が、もっとも見落としやすい部位として知られています。
すなわち、この高位の「麻痺は頚髄節が損傷を免れるため上肢の麻痺を欠き、対麻痺の形をとる。したがって胸椎レベルの損傷が疑われ画像診断が行われるため頸胸移行部は画像から外れるか、もしくは画像の上端部にかろうじて写っていることになり、医師の関心領域を外れるため見逃しが起こりやすい。さらに単純X線側面像ではちょうど肩の陰影と重なってまったく読影できない。損傷部位の特定できない対麻痺は、CTスキャンやMRIを駆使して頸胸移行部を検索することが肝要である」(「整形外科専門医になるための診療スタンダード 1 脊椎・脊髄」P228)としています。
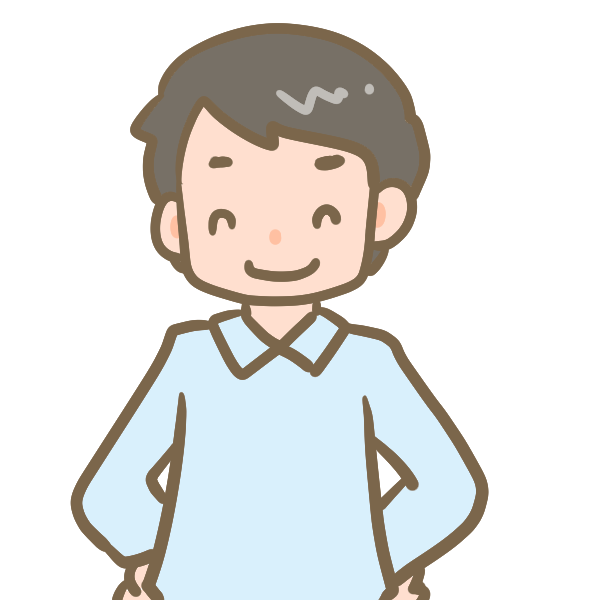
主治医の単純ミス
患者が訴えていたのに、カルテなどに記載しなかったケースです。たとえば痺れの記載漏れがあったために、受傷直後に痺れの訴えがなかったとして、脊髄損傷の後遺障害認定をはねられるケース。よくありますね。
以下の理由は毎度おなじみのものなので、項目だけあげ、説明を省きます。
重篤な合併症の存在
軽い訴えだったための見逃し
既存障害との混同
肩外傷の存在
非骨傷性脊髄損傷に関する裁判所の判断の傾向
「(裁判所の姿勢は)脊髄を保護する脊椎に骨折・脱臼が生じている場合には、脊髄損傷の存在を裏付ける有力な他覚的所見となるが、逆に、骨折・脱臼のない、いわゆる非骨傷性の脊髄損傷の場合には、脊髄損傷自体の存否が争いになることがある。しかし、脊髄に何らかの異常所見が認められ、脊髄の障害によるものと思われる神経学的な異常が認められる例では、脊髄損傷等が肯定されることが多い」(前掲書P341)。
逆に、「画像所見もなく、神経学的な異常所見もなく、ただ感覚障害や疼痛だけを訴えている場合に、脊髄損傷の発生が認定されることはまずない。しかし、異常所見があっても、脊髄損傷が否定されることはもちろんある」(前掲書P255)。
非骨傷性頚随損傷に関する裁判例
非骨傷性頚随損傷について自賠責では後遺障害と認定されなかったものを、事故との因果関係を認め、後遺障害7級を認定した平成25年5月30日仙台地裁判決があります。詳細は小松弁護士HPで確認してください。
他にも、以下の判例があります。
大阪地裁 平成7年3月2日判決
事故直後排尿困難を訴えて軽度の下腹部緊満が認められたほか、顔面に冷や汗をかき、苦痛の表情で「身体を触らないでくれ」と言い、腰部痛および右肘から手先の痛みを強く訴え、ピリピリした痺れが少し認められ、事故を機に自力歩行が相当に困難な状態が発現した。被告は先天性奇形体質(クリッペル・ファイル症候群)やヒステリー・賠償神経症等の心因性要因によるものお主張し相当因果関係を争った。
裁判所は、①脊髄損傷の初期症状との類似性②本件事故を機に自力歩行が相当に困難な状態に発現したこと③ほぼ一貫した胸椎11髄節以下の知覚障害の存在④他覚的所見として胸髄MRI検査により胸椎10―11椎体レベルの胸髄内に細長いT2強調信号を認め(脊髄梗塞ないし脊髄損傷の可能性)、③と符合すること⑤原告の症状には脊髄ショック等脊髄損傷の典型的な諸徴候が認められないものの、脊髄損傷の部位・程度によって当該徴候の有無・程度には相当広範囲な差異があり、画像診断で捉えられない脊髄損傷も存在することを総合考慮し、本件事故による外力が原告の脊髄(胸椎10―11椎体レベルの胸髄内)に損傷等を与え、両下肢麻痺の一因となったとした。
また、症状固定時期ころの垂れ足検査で床に足を打ち付けなかったこと等を踏まえ、症状固定時の両下肢麻痺の程度は、後遺障害診断書の記載から窺われる程度よりやや軽い程度と推認し、両下肢の筋力自体は徒手筋力テストで2ないし3のレベルで、両下肢には軽度の筋委縮が認められる程度の自力歩行が困難な不全麻痺(5級2号)であったと認定した。さらに、素因減額として、既存の軽度の精髄疾患の影響や心因的要素の関与から4割を認定した。
神戸地裁 平成11年1月11日判決
事故直後に入院した医療機関におけるレントゲンにも骨損傷などの異常所見はなく、MRIでも異常所見はないことなどから脊髄損傷の存在が争われた事案。後医のMRI検査の結果はT1水平断における第3頚椎レベルの頚髄内の右側寄りに低信号域があるように見えることから、頚髄に出血があって、それが治まって、痕跡が繊維化していると推定されること等を総合して、本件事故により頚髄損傷の障害を受けたもの(脊髄空洞症)と診断し、現在の症状はその後遺障害であるとの診療医の証言、さらにはこれに疑問を呈しつつも、その診断を否定せずかつ事故との因果関係を完全に否定できないという鑑定医の意見を根拠に事故との因果関係を認めた。が、頚椎管狭窄が生じており、頚髄損傷を起こしやすかったこと、通常の経過をたどっていないことなどから、50%の寄与度減額を行った。
典型的な経過をたどっていないことケースであり、また、原告自身の供述に疑問を呈しながらも、脊髄損傷を推測させる画像上の根拠がいちおう存在し、かつ、鑑定医診察時点で両側の上下肢に明らかな腱反射の病的亢進がある等、客観的な症状の存在が因果関係肯定につながったと推測される。
つい最近にみつけた裁判例
調査員だったときに集めていた資料の中に、こういう裁判例を紹介している資料をみつけました。概略以下のとおりです。
50歳男性が乗用車を運転停止中に追突された。物損はバンパーの凹みのみ。 初医では「頚椎捻挫(むち打ち症)」と診断されA病院へ 3か月通院。 症状が増悪したため、B整形外科へ転医し、そこで「外傷性頚髄障害」と診断され100日間入院した。
入院中に、C大学病院を照会され受診したところ、手術の適応ありと診断され、脊柱管拡大術が行われた。 その後も、巧緻運動障害や膀胱直腸障害は改善しないまま、受傷から1年半後に症状固定とされた。
受傷者は、頚髄損傷による後遺障害として8級2号を主張して、訴訟提起した。
相手損保の主張。「事故の状況から、頚髄損傷を起こすほどの外力は加わったとは考え難く、現に当初は頚髄損傷とは診断されていない。後日頚髄障害が生じたとしても本件交通事故とは直接の関係はない」。
仮に関係があったとしても、「事故直後の画像検査資料で、既存の脊柱管狭窄症(後縦靱帯骨化症)があり事故を契機に症状が出現したもので、既往疾患の関与が大きい」。
【判決】
「大きくない衝撃で経時的に症状が悪化したのは、既往症(脊柱管狭窄症)の寄与があったとして、 5 割を減額」した。
本件は、事故から 1か月以上経過して初めて脊髄症状が出現している点がポイントですね。それでも後遺障害を認定している点です。