【ギリシャ神話の中のシリンクス(SYRINX)】
目次
相談
4日前に相談があった事案です。相談者は信号待ちのところを後続車に追突され、相談者は頚椎挫傷、隣に同乗していた夫が脊髄空洞症だったそうです。電話でおおよその概要を聞いて、期待にそえるかわからないが、資料を送っていただくことにしました。
脊髄空洞症について
頚椎挫傷についてはすでにいくつか記事にしているので、本日は脊髄空洞症について記事にしたいと思います。以前、脊髄空洞症についても書いたことがあったので、それに後遺障害認定の際に重要と思われる点を加えるなどして、大幅に加筆しました。医学的にむずかしい話は私にはさっぱりわからんから、最小限にとどめました。医学書等で確認してください。
脊髄空洞症というのは、いわゆる「難病」のひとつで、男女差はなく、発症年齢も20代~30代がメインで、10歳以下や50歳以上ではほとんど見られないものです(文献によっては10歳以下でも多いとの記載あり)。脊髄の中に髄液がたまって、文字通り、脊髄の中に空洞ができたかのようになることです。脊髄に空洞ができると、その内圧の関係でそれが周辺の神経を圧迫します。圧がそれほど高くなかったとしても、何十年とたつうちに空洞周囲の組織をわずかづつ損傷して様々な全身症状が現れます(注1)。
(注1)
なお、髄内腫瘍に伴うものは、腫瘍組織に伴う嚢胞として、脳脊髄液の循環動態の異常を基盤とする空洞症と区別されて論じられることが多い。
ところで、脊髄は背骨の中にあって、脳からの指令を身体の末端の各部に伝えたり、逆に、末端からの情報を脳へ伝える働きをします。その大切な脊髄にぽっかり空洞ができて、神経を圧迫するわけですから、情報のやりとりを阻害したり、神経障害が発生したりします。そして、空洞は進行することが多く(注2)、最初は小さな空洞だったものがそのうちにだんだんと縦横に大きくなって(ただし、背部には進行しない)、最後は脊髄自体がちくわのような形状になってしまうという、なんとも恐ろしげな病気です。
下のMRI画像は脊髄空洞症であることを示しています。

【キアリ奇形Ⅰ型 出典:秋田県立脳血管研究センター】
不謹慎な表現ですが、まるでミミズが這っているというか、ちくわのような形状なので、私のようなシロウトでも一目瞭然でわかります。
脊髄空洞症はMRIが発達することで診断が進みました。つまり、以前は奇病扱いだったものが、歴史的に新しい病気として認知されたものです。そして、MRIの高解像度により、ごく初期の段階でもみつけることができるようになったわけです。しかし、空洞の大きさや位置と症状の関係は解明されていないと言われています。また、空洞は長い年月をかけて大きくなっていくため、手術をしても、せいぜい現状維持、すなわち、すでに発症した神経症状や筋の萎縮は元に戻らないと言われております。画像で空洞がなくなっても、症状の改善がみられないということもあります。そのため、できるだけ早期に診断し、処置を考えることが必要です。症状の進行するものが60~70%、進行停止あるいは改善するものが20~30%です。(「標準整形外科学」(医学書院)より)
下図が脊髄空洞症にかかったときの脊髄の横断面図です。進行すると、→で示されたような拡がりを示し、神経症状も変化するといわれています。

【出典:「病気が見える 脳・神経編」メディックメディア P201】
「病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経 (Medical Disease:An Illustrated Reference)」
事故との関係が争点になる
後遺障害認定の際に争点となるのは事故との因果関係です。事故との因果関係ですが、ふたつのことに注意してください。ひとつは、脊髄空洞症が外傷性のものかどうかということです。もうひとつが、軽微な事故との関係です。この2点で争いになることが多いのです。相談者のケースは、後者の軽微な事故だったことを理由に、相手損保および自賠責から事故との因果関係を否定されていました。
脊髄空洞症の原因疾患
脊髄空洞症は単独の疾患ではなく、①キアリ奇形(小脳の一部が脊柱管内に落ち込んでしまっている状態)、②脊髄外傷、③脊髄くも膜炎など、いろいろな疾患による二次的変化として、脊髄内に空洞が形成されると考えられています。そこで、まずはどのような原因で二次的に脊髄空洞症を発症するのかから始めたいと思います。下図は、東京慈恵医科大脳神経外科の、脊髄空洞症を原因別に年度ごと集計した表です。「キアリ奇形」を原因とするものが圧倒的に多い。過去5年間の311例中251例がそうでした(全体の80.7%)。

ところが「外傷性」のものは311例中48例しかありません(全体の15.4%)。他は、水頭症など原因がいくつも考えられるものや、原因不明なもの(特発性等)、内因性と思われるものです。
この中で「外傷性」とあるのは脊髄損傷由来のものです。以下に「標準整形外科学」(医学書院)の分類例も参考のために示します。
| 脊髄空洞症を生ずる基礎疾患 | |
|---|---|
| 先天性疾患 | キアリⅠ型 |
| 先天性疾患 | キアリⅡ型 |
| 先天性疾患 | 水頭症 |
| 後天性疾患 | 脊髄損傷 |
| 後天性疾患 | 脊髄腫瘍 |
| 後天性疾患 | 癒着性くも膜炎 |
| 後天性疾患 | 脊柱側弯炎 |
| 後天性疾患 | 脊髄動静脈奇形 |
| 後天性疾患 | 圧迫性脊髄症 |
| その他 | |
「標準整形外科学」
「標準整形外科学 第14版」
キアリ奇形だと後遺障害認定は絶望的なのか
相談者の夫の基礎疾患(原因となる疾患)が何なのかを質問したのはいうまでもありません。キアリ奇形? それには反応はなく、主治医からは先天性のものだと告げられたそうです。先天性? それが事実なら、キアリ奇形か水頭症ということが考えられます(注)。いずれにしても、後遺障害認定はかなり困難な状況です。ネット情報では、キアリ奇形では後遺障害獲得はありえないとしているところばかりです。相談者のケースについていえば、事故が軽微だったこと、脊髄空洞症が先天的なものだということ、つまり、2段構えで問題点があります。
(注)ネットで調べてみたところ、キアリ奇形でも後天的な理由で発症する場合があり、それも事故が原因だとされていました。さらに調べてみると、その「事故」というのは、「出産時の外傷(難産、鉗子分娩など)」(「精髄空洞症(syringomyelia)のすべて」)のようです。交通事故とは無関係だといえそうです。
キアリ奇形かどうかの判定基準
もっとも多いキアリ奇形かどうかの判定基準は、大後頭孔から扁桃下端までの距離を計測して決めます。3ミリまでなら正常範囲、3~5ミリは境界領域で、5ミリ以上だと病的下垂と判定される。しかし、空洞症は境界領域の下垂でも合併するから、3ミリを基準にすべきという意見もあります。
外傷性脊髄空洞症の判定基準
ところで、事故との因果関係が明確に肯定される外傷性のものは、先に説明した「脊髄損傷」型です。「脊髄損傷」型の特徴として、以下のことが医学書に書いてありました。
②脊髄損傷ではときに損傷後数年で損傷高位より中枢側に空洞が拡大伸展することがある。このため、健常高位に新たな神経症状や痛みが生じ、対麻痺が四肢麻痺となることがある。
(以上、「整形外科専門医になるための診療スタンダード1 脊椎・脊髄」P235より)
このように、脊髄空洞症は「キアリ奇形」を原因とするものが非常に多いのに対し、外傷性のものは少ない。今回ご相談の件は、外傷性のものではなく、先天性のものだと主治医から言われている。先天性だから、「キアリ奇形」なのかもしれない。ただし、事故前の発症はなく、今回事故にあったことでMRI画像を撮ってみたら、脊髄空洞症であることがわかったということです。つまり、事故前は症状がなく、事故が引き金になって発症したケースです。
裁判所は、閾値論否定による引き金論の救済がありうるのか
結論を言ってしまえば、自賠責は先にも書いたように2段構えで否定してくるでしょう。だから、このケースは裁判しかありません。では、裁判だとどういう判断になるかです。ここでは第一に裁判所は閾値論をどう判断しているのか(参考記事「軽微な追突事故と頚椎捻挫との因果関係」。最後の「関連記事」からアクセスできる)、第二に、脊髄空洞症のような難病について引き金論による救済がありうるのかです(関連記事:「椎間板ヘルニアを例にして、外傷性であることの立証が困難な場合の対処法」)。すなわち、ひとつの方向としては、
事故前に往診歴等もなかった。
症状を訴えた原因箇所が画像で確認できているし、症状についてもそれで説明できる。
以上の理由があっても、外傷性そのものが立証されたわけではないから、後遺障害を否定する(自賠責の考え方)。もう1つの方向は、以上の条件がそろえば事故との因果関係を認める。しかし、その真偽不明の部分(もしかしたら外傷でないかもしれない部分)を素因減額として調整する。
椎間板ヘルニアについては事故との因果関係を認めているのが裁判所です。問題は、椎間板ヘルニアはだれもがかかるような傷病名であることです。つまり退行性変性疾患なのであり、老化の一種ともいえます。しかし、脊髄空洞症はだれもがかかるような傷病名ではありません。難病です。その違いが裁判でどう影響するかです。
ここで有名な最高裁の判例を紹介します。ひとつは「首長判決」です。もうひとつは、「後縦靭帯骨化症という難病に対する判決」です。(以下は、後日加筆修正予定。)
「寄与率と非典型過失相殺」より
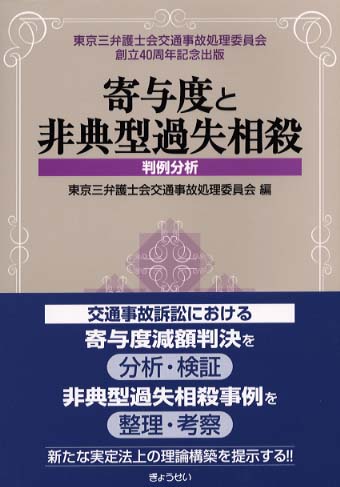
実際の脊髄空洞症例
脊髄空洞症に関する裁判例
事故との因果関係のある・なしや素因減額で争いになりやすい。そこで、脊髄空洞症と事故との因果関係や素因減額に関する判例をいくつかご紹介する。
【基礎疾患が脊髄損傷の因果関係肯定例】
事故直後に入院した医療機関におけるレントゲンにも骨損傷などの異常所見はなく、MRIでも異常所見はないことなどから脊髄損傷の存在が争われた事案である。
MRI検査の結果(T1水平断における第3頚椎レベルの頸髄内の右側寄りに低信号域があるように見えることから、頸髄に出血があって、それが治まって、痕跡が繊維化していると推定される)こと等を総合して、本件事故による頸髄損傷の障害を受けたもの(脊髄空洞症)と診断し、現在の症状はその後遺障害であるとの診療医の証言、さらには、これに疑問を呈しつつも、その診断を否定せずかつ事故との因果関係を完全に否定できないという鑑定医の意見を根拠に事故との因果関係を認めた。
しかし、頚椎管狭窄が生じており、頸髄損傷が起こしやすかったこと、通常の経過をたどっていないことなどから、50%の寄与率減額を行っている。
【若年者の非骨傷性の脊髄損傷における因果関係肯定例】
非骨傷性脊髄損傷の事案である。脊髄内病変につき、被告は特発性脊髄内出血として、事故との因果関係を争った。
裁判所は事故に遭遇する以前の段階では、既存障害による若干の症状を除き上肢機能に顕著な障害が存在した形跡がなかった。しかし、本件で認定される重篤な上肢(特に右上肢)機能の障害は、本件事故後2週間以内には発症したものであるとした。
従前は見られなかった重篤な上肢機能の障害が、本件事故後まもなく、事故とは関係のない原因不明の頸髄髄内出血によって突発するという可能性を全く否定することはできないにしても、事故前後にわたる上記症状の推移に照らせば、事故とは関係ないが原因は不明という頸髄髄内出血を想定することの不自然さ、不可解さを払拭し得ないことが指摘されること、乳幼児や16歳くらいまでの若年者における骨傷を伴わない頸髄損傷(放射線的異常を伴わない外傷性脊髄損傷)では、脊髄への直接圧迫のほかに、脊髄の屈曲や伸張も受傷機序にあると考えられている。
本件事故当時、原告花子は18歳の女性でまだ脊椎の柔軟性があり、受傷時に車両の下敷きになった際、頚椎から上位胸椎が高度に前屈や後屈あるいは伸張されたとすれば、
①胸髄は強い屈曲と長軸方向への牽引力により屈曲、伸張され、胸髄の骨傷を伴わない脊髄損傷を合併したとも考えられること
②頸髄についても胸髄と同様の受傷機序で頸髄の強い屈曲や伸張が加わったことにより骨傷を伴わない脊髄損傷を起こしたものと考えられること
③頸髄部の髄内病変が外傷による骨傷を伴わない脊髄損傷であったとすれば、脊髄の挫滅による脊髄壊死や脊髄浮腫の程度、範囲が受傷後徐々に悪化、拡大し、受傷後数日の無症状期間を経てから症状が徐々に出現してくることはあり得ること
④発症後の麻痺の悪化、拡大とその後の改善は外傷性脊髄損傷の急性期に比較的よく見られるものであり、平成11年11月1日に得られた第4~第7頚椎レベルの髄内における嚢腫様の空洞を示す所見は、脊髄損傷の慢性期に見られる、いわゆる外傷後脊髄空洞症の画像所見と思われること
などを指摘し、原告の頸髄の異常は、本件事故による頸髄損傷であるとの診療医の意見を踏まえ、事故と脊髄損傷との因果関係を肯定した。
【遅発性麻痺が外傷で発生する場合を限定した上で事故との因果関係を肯定し、それ以外を否定した例】
骨傷のない頸髄損傷(急性中心性頸髄損傷)は、加齢変性による頸部脊椎症や後縦靭帯骨化症による脊柱管狭窄のある者に頻発し、受傷の瞬間から四肢麻痺が発生する。
受傷時麻痺がない、遅発性頸髄麻痺が外傷で発生することはまれであり、外傷による頚椎脱臼、骨折が発生し頚椎不安定症を生じ、2次的に頸髄麻痺が発生してくる場合、外傷により頚椎骨折が発生して出血による血腫で頸 髄を圧迫して頸髄麻痺が発生する場合、外傷性頸髄空洞症により麻痺が発生してくる場合以外にはない。
以上、「後遺障害等級認定と裁判実務」(新日本法規)より。
【遅発性麻痺が外傷で発生することを肯定した例】
年齢 26歳
性別 男子
事故日 昭和55年7月7日
原告の傷害内容 頭部外傷Ⅱ型、第7頸椎/第1胸椎脱臼骨折等
自賠責等級 8級相当(なお、昭和57年9月2日に8級相当で示談成立)
裁判所認定等級等
神経症状5級2号(上記8級の加重障害と認定)
喪失率34パーセント(5級79パーセントから8級45パーセントを引いた)
喪失期間67歳までの22年間
原告が主張する後遺障害の内容
原告は、本件示談契約を締結して、いったん示談したものの、その後本件事故による頸椎脱臼骨折後の外傷性脊髄空洞症及びすべり症の悪化により、右上肢及び左下肢の著しい機能障害、右下肢全廃、排尿障害及び性機能障害の後遺障害を残した。
上記後遺障害は、等級表2級3号(神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)に該当する。
被告の主張
原告は、上記示談後約15年間にわたって治療を受けておらず、本件事故以外の原因によって症状が現れたのであるから、本件事故と原告の現在の症状とに因果関係はない。
主治医の見解
脊髄空洞症の原因としては、外傷のほかに、脊髄腫瘍、キアリー奇形等があるが、MRI上脊髄腫瘍は認められないし、キアリー奇形もMRI上見られない。また、キアリー奇形による脊髄空洞症は頸椎に発生することがほとんどであり、胸椎に発生することはほとんど考えられない。そして、頸椎の損傷部分の直下に脊髄空洞症があることを考えると、その脊髄空洞症は外傷によるものと考えるのが一番妥当である。
また、外傷性脊髄空洞症は、外傷後10年以上経過してから発症してくることが多く、30年以上たってから発症することもある。現代医学では、脊髄損傷後、何年間かしてから症状が増悪していれば、まず外傷性脊髄空洞症を考えるのが常識である。
鑑定医の見解
原告の第2胸椎、第3胸椎椎体後方に紡錘形、嚢胞状に脊髄空洞症が存在し、その程度は中程度である(平成8年のMRI画像による。)。
外傷性脊髄空洞症の多くは遅発性であり、受傷後1年以内にこのような状態になることはまれであり、通常は2年ないし3年程度でこのような状態になる。外傷性のものはしばしば嚢胞変性をきたす。また、脊髄空洞症はMRIの機器がなければ容易に診断することができないが、MRIの機器が普及したのは1990年代であり、それ以前には基幹病院以外では使用されていなかったので、本件事故当時、A病院で脊髄空洞症を診断することは困難であったと思われる。また、全く関係のない疾患による嚢胞型脊髄空洞症の発生は考えにくい。
保存期間経過のため本件事故直後の診療録等がないので断言はできないが、以上のことからすると、本件事故後平成8年までの間に、頸部に何らかの大きな外力を受けるようなことがなければ、本件事故により脊髄空洞症が発症した確率は極めて高いと思われる。
原告の訴えている症状は、脊髄不全損傷であり、かつ、中心型であるから、脊椎管狭窄あるいは神経鞘腫摘出術後の症状である可能性はほとんどなく、全く関係のない神経疾患が嚢胞形成とは別に存在するという考え方にも無理がある。したがって、原告の訴える各症状は脊髄空洞症が責任病巣であると思われるが、脱臼骨折そのものによる神経の圧迫障害も症状の重症化に関与している可能性はある。
原告は、本件事故により、第7頸椎を脱臼骨折し、それにより第7頸椎が前方移動して前屈した結果、第7頸椎の前方偏位を来しており、結果的にすべり症と同じ状態になっているが、約35度の前屈位で変形を残しており、程度としては軽度である。
以上から、原告の症状は、脊髄空洞症が主たる原因であり、すべり症が直接的な責任病巣なのではなく、あくまで副次的な要因に過ぎない。
【裁判所の判断】
原告は、本件事故により第7頸椎/第1胸椎脱臼骨折、脊髄損傷などの傷害を負い、それにより遅発性の脊髄空洞症を発症し、その結果、歩行障害や両下肢のしびれなどが現れたと認められる。したがって、本件事故と原告の上記症状との間の因果関係が認められる。
原告の後遺障害は、前記認定のとおり、平成11年7月ころには歩行に際し、平地においても杖等を要すること、上下肢及び明らかな躯幹にも知覚障害があること、膀胱障害のほか性機能障害もあること等に照らし、労働能力のかなりの部分を失ったと考えられ、後遺障害別等級表の5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当し、その労働能力の79%を喪失したと認めるのが相当である。
被告らは、原告がA病院への通院を終えてからB病院を受診するまで約11年間もの長期間何らの治療も受けていないこと、上記期間において何の事故もなかったとはいえないことから、本件事故と原告の症状との間に因果関係がない旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、原告の脊髄空洞症は遅発性であり、外傷後10年以上たってから発症することもあり、受傷当時MRIによる確定診断も難しかったから、原告が脊髄空洞症による症状発症までの間、長期間治療を受けていなかったからといって不自然ではない。
また、別の事故の可能性も、そのような事情があったことを窺わせる証拠は全くない。かえって、前記認定のとおり本件事故を原因として発症したと考える方が自然である。したがって、被告の上記主張は、いずれも失当である。
以上、(自保ジャーナル第1387号)より
【因果関係および素因減額が争点になった例】
大阪地方裁判所平成14年12月13日判決
(自保ジャーナル第1491号)
年齢59歳
性別男性
職業自称運送業(判決では運送業に従事していた事実は認められなかった。)
事故状況
原告が高速道路で普通貨物車に同乗中、被告運転の乗用車に追突され、玉突き事故となった。
後遺障害等級
原告主張:1級3号
自賠責:加重障害1級
裁判所認定:1級3号
原告の主張する後遺障害の内容
非骨傷性頸髄損傷、左手・両下肢麻痺
素因減額75%
素因(既往症)の内容
脊髄空洞症・過去の交通事故の後遺障害
備考
原告の事故当時における身体状況からすれば、事故当時就労していた事実は認められず、将来において就労する蓋然性があったとは言い難いことから、休業損害と後遺症逸失利益は認められなかった。
本裁判例の内容
本裁判例は、玉突き追突事故の被害を受けた原告が、非骨傷性頸髄損傷の傷害を負い、左手、両下肢麻痺の1級3号の後遺障害を残したとして訴えを提起し、因果関係及び素因減額が争われた事案である。
原告にはもともと血管芽細胞腫(脊髄腫瘍)に伴う脊髄損傷空洞症の既往症が存在した。さらに原告は、昭和59年11月の交通事故により後遺障害3級3号が残り、前件事故における損害賠償請求訴訟(大阪高裁平成2年(ネ)第2512号においても、原告の後遺障害は3級3号、後遺障害に対する事故の寄与割合は2割(脊髄空洞症の寄与割合が8割)と判断されていた。
原告の損害賠償請求に対し、被告は、原告が脊髄空洞症等の既往症及び過去の事故の後遺障害により、既に1級3号に該当する状態にあったものであり、原告主張の損害と本件事故との間に因果関係はない、仮に因果関係があるとしても、本件事故の寄与割合は1割以下であると主張した。
裁判所は、原告が本件事故以前には杖を用いながらも自力で歩行できていたにもかかわらず、本件事故直後に両肩以下がほぼ完全麻痺となり、治療及びリハビリの結果、右手は若干動かせるものの、左手及び両足が完全麻痺の状態となったことからすれば、本件事故と原告の受傷及び後遺障害の発生には因果関係があるとした。
しかし、裁判所は、①原告にはもともと血管芽細胞腫に伴う脊髄空洞症の疾患があり、同疾患は脊髄の機能を障害するものであること、②本件事故による衝撃は比較的軽微であること(原告と同乗していた原告の息子は加療約13日間を要する頸椎挫傷を負ったにすぎない。)、及び③原告の頸髄損傷も非骨傷性のものであることから、原告の後遺障害は本件事故の衝撃のみによるものではなく、既存の疾患である脊髄空洞症もその原因になっていると考えられると認定した。
そのうえで、裁判所は、脊髄空洞症と前件事故とが相まって生じたとされる後遺障害が残存していたこと、脊髄空洞症は進行性のもので、原告は本件事故がなくても5,6年後には車椅子の使用が必須である可能性があったことからすれば、原告に生じた損害の全部を被告に賠償させるのは公平を失するものであるとし、損害の公平な分担の見地から、損害額の75%を減額した。
(以上、「交通事故の脊髄損傷」より)

