以下の文を読んだ目撃者は、やはり目撃証言はやるべきでないと思われたかもしれません。もしそう思われた方がおられたら、それは私の説明不足です。法的な責任はなくとも、事件あるいは事故の解決に資するかもしれない道義的責任はあると、私は考えるからです。
目次
目撃証言することをあえて無視することはできるが
事件や事故を目撃し、それを証言することは解決に資することなので、たいへん大切なことです。目撃者は捜査に協力する義務などありませんから、目撃証言をすることをあえて無視しても制裁を科されるわけではありません。
しかし、大変な苦労をして目撃者捜しをしてみたが、いるはずの目撃者が現れなかったためにその事件や事故が解決しないことは、その被害者はとって不幸なことです。そういうことがないようにするためにも、やはりできるだけ協力すべきだと思います。
ただ、その協力の仕方が問題になります。目撃と言っても過去の体験を今になって思い起こす作業であるために、そこにはある種の曖昧さを含むものです。その曖昧さをあえて断定して語ることは慎まなければならない。そこは本当に注意すべき点です。なぜそうなのかがこの記事の主題です。
保険調査の目的は保険会社に有利な証拠集めのためである
保険調査という仕事の目的は「真実の探求」だと建前上言われているけれども、それはあくまで「タテマエ」です(苦笑)。示談するための損保にとってより有利な材料探しがその真の目的だからです。それは子飼いの調査会社であっても外部の調査会社であっても事情はまったく同じ。示談というのは民事上の折り合いをつけることであり、刑事事件の目的である「真実の探求」などは民事の保険調査においては2の次、3の次のことだからです。
とはいっても、個々の調査員の中にはけっこう職人気質の人もいて、示談の結果がどうなるかなんてどうでもよく、「真実の探求」を目指すことにやりがいを感じている人がごく少数ながらいます。しかし、そういうタイプの人を会社組織は必要としない。真実にこだわっていたらテマヒマがかかりすぎるため、採算ベースに乗らないからです。調査員は、案件をよりスピーディーにより多くこなし、会社に利益をもたらすことがなによりも求められる。
だから、会社から評価され有能といわれる調査員はいかに無駄を省くかに腐心しています。そういう考えでないと収入にならないし、いずれ会社から放擲される運命にあるからです。そういう考えの人は下で紹介するような本にまず興味を示さない。証人の証言がどこまで信用できるかなんて本気で考え出したら、ソラ恐ろしいことだからです。そもそも、そういう疑問すら抱かないでしょう。
人の記憶に頼りすぎると冤罪の温床になりかねない
人の記憶は想像以上に容易に変化し得る
[amazonjs asin=”4000252895″ locale=”JP” title=”目撃証言”]エリザベス・ロフタフの「目撃証言」という本を、調査員になりたてのころに図書館から借りて来て読んだことがあります。人間の記憶というものがいかにいい加減なものなのかを実証してみせた傑作です。
そのため、著者は、証人の証言は冤罪の温床だとまで書いています。この本を読みたいと思ったのは、調査員をやっていた当時、目撃証言がどこまで信頼できるのか疑問に思ったからです。アマゾンの書評を引用することから始めます。
刑事裁判において、物証に乏しく、目撃者の証言によって被告の有罪か無罪かが決まることがあります。犯人を目撃した数名の人物が特定の一人を「犯人」と識別したとしたら、それは極めて強い証拠と感じられるでしょう。
ところが、頑強と思える目撃者証言の有効性に、本書は強い疑問を投げかけます。被害者もしくは数名の目撃者が自信を持って「無実」の人を犯人と断定することがあること、人の記憶は想像以上に容易に変化し得ること、そしてその事実は人々に知られていないことを教えてくれます。
ラインナップ捜査は信頼に値しない
容疑者などの特定の人物と、数名の無関係の人物を並ばせて目撃者に識別させる方法をラインナップと呼ぶ。下の画像はそのラインナップです。

ラインナップを実施する際に注意しなければならないことは、目撃者はラインナップの中に容疑者がいるはず、そうでないと警察がラインナップを実施するはずがないと信じている傾向があることです。そのため、ラインナップのいかなる人物も目撃者の記憶と正確に一致しない場合でも、もっとも似ている人物をしばしば選んでしまうことがあることです。そこでそういうことにならないようにラインナップに並んでいる人物は年齢も姿形も似ていないとまずい。
そうであるべきなのに、この本ではこういった例が紹介されています。
ミネソタのある事件のラインナップでは、1人の黒人容疑者の横に5人の白人が並んでいたし、6フィート3インチの容疑者が、全員5フィート10インチ以下の身長の、容疑者でない人物たちの中に置かれるというラインナップが行われた事件もあった。犯罪者が10歳代であることがわかっている事件で、18歳の少年が5人の40歳代の容疑者でない人々のラインナップの中に置かれたというのもある。・・・
目撃者が公正なラインナップ(そこではすべての人物が少なくともほぼ同じような身長、体重で、全体的な身体的特徴が一致している)を示されたと考えてみよう。その目撃者が一所懸命に集中して見ているときに、警察官が突然、「4番をもう一度見てください」と言ったとしよう。警察官は、目撃者が犯罪者を識別しようとしているときに、4番をやたら見つめるかもしれない。また目撃者が4番を見ていて躊躇しているときに、身をのりだして「その人物についてはどうです?」と言うかもしれない。
証人はこれらのほんのささいな情報を受け取り、写真の人物のイメージとともに、漠然としてあいまいな記憶を「満足させる」ために、無意識に、それらの情報を使用するかもしれない。イメージは変化し、輪郭線は揺らぎ、突如として4番の顔が犯人の消えゆく記憶と融合する。「4番の人が似ています」と目撃者は言うかもしれない。そして、しまいには「はい、たしかに4番です」と。(P26‐)
著者のエリザベス・ロフタフは、「実際の犯罪事件に使用されるラインナップはほとんどが暗示的で、目撃者の識別には価値がないと考えるべきである」と結論づけています。この結論はかなり衝撃的ですね。
基盤となる記憶を推測が実質的に変化させてしまう怖ろしさ
アマゾンの書評に戻ります。そこでは「人の記憶は想像以上に容易に変化し得ること」と書いてありました。それはどういうことでしょうか。ネット検索したらすばらしい紹介記事を見つけたのでそこから引用します。
この本を読んでいると、被害者になったり、事件を目撃したりといった強いストレス下で蓄えられた記憶は、警察官からの有形無形の圧力を感じたり、警察官が無意識的にでも誘導を行なったり、時間が経過したり、新聞報道などの事後情報に晒されたりすると、あっさりと書き換えられてしまうことがわかります。
推測を行なうことよって記憶がどう変わるのか、変わった後にはどう固定されるのかについて、本文から抜粋します。
>…推測は特に危険である。というのは証人が確信をもてない場合には、推測がその出来事に関する最初の骨格となる描写の隙間を埋めてしまい、基盤となる記憶を実質的に変化させてしまうからである。のちに記憶をたどるときに、証人は記憶に隠されていた部分として、最初は推測にすぎなかったものを実際の記憶であるかのように誤って再生するかもしれないのである。さらにはじめの推測が比較的低い自信とともに表明されていても、あとで推測したことを実際の記憶として誤りを犯すような場合には、その自信の程度が強まるのである。証人は、もはや当初の事実をそのあとの推測から区別できなくなり、心ではその作り物を真実として理解してしまう。事実は推測に塗り固められてしまうのである。
記憶を大きな堤に積み上げられ、組み合わされたレンガ(いろいろな詳細、事実、観察、そして知覚)の蓄積であると想像してみるとよい。推測はそれらのレンガにピシャッと塗り付けられたセメントであり、レンガを堅く、密着した構造に仕上げるのである。最初、推測は液状で可塑性があるが、時間の経過とともに固められ、堅くなり、変化しにくくなる。そして記憶が呼び起こされるたびに、推測されたことが生き生きとして、しかも色彩にあふれ、いっそう現実味を帯び、ありのままのものであるとの自信を証人は深めるようになる。
実際の犯罪における識別の手続きでは、警察や検察官は目撃者に完全でしかも正確であるようにと、微妙ではあるが重い圧力をしばしばかけてくる。そのような圧力にさらされて推測がすばやく凝固される。目撃者も自分自身に圧力をかける。不確実なものや混乱したものを避けようとするのが心の一般的特徴である。一度でもそれに応えてしまうと、それに縛られ、時間の経過とともに自信を持つようになる。事実として述べた供述を再考したり、それに疑問をさしはさむことは、名誉や高潔さに反すると感じられるのかもしれない。<
どちらが信号無視したのか不明の事故では、目撃者探しが始まる
保険調査においても第三者の証言というのはかなり重要視されています。たとえば信号のある交差点で双方青主張の出合い頭事故があるのですが、双方青ということはありえないから、どちらかがウソをついているか、勘違いしている。はてさて、どちらの言い分が正しいのか、調査員は迷路に迷い込んでしまいます。
たいていの事故は物証が決め手になるのに、信号の色がわからない事故については、クルマの破損やブレーキ痕などのいわゆる物証をいくら丹念に吟味しても、信号が何色だったのかはわからないからです。
それで安易に目撃者を探せということになります。だれか目撃している人がいないかなあと事故現場周辺に聞き込みをしたり、事故発生と同時刻に現場に行き、行き交う車の運転者にわかるようにのぼりを立てて、目撃者探しをしたことも、依頼先の要請であります。目撃者に頼る傾向は、警察も同じです。
目撃者がすぐに見つかればいいのだけれども、時にはそれが2週間後だったり、1か月後だったりします。記憶は時間の経過とともに薄れ、そこに後付けの推測が加わり、固定化される傾向にあることは、エリザベス・ロフタフの強調するところです。
たとえば20日前の午後7時30分から午後8時まで何を目撃したのか。などと聞かれて正確に詳細に答えられる人はほとんどというか、まったくいないはずです。少なくとも、私にはまったく答えられない。
そうは思うはずなのですが、ときどき、あとから目撃者が見つかったと言ってきて、詳細に答える目撃者があらわれたりします。そういうときは、どの位置から目撃したのかなど事故時の目撃の詳細だけでなく、その目撃者と事故当事者との関係も疑ってみる必要があります。
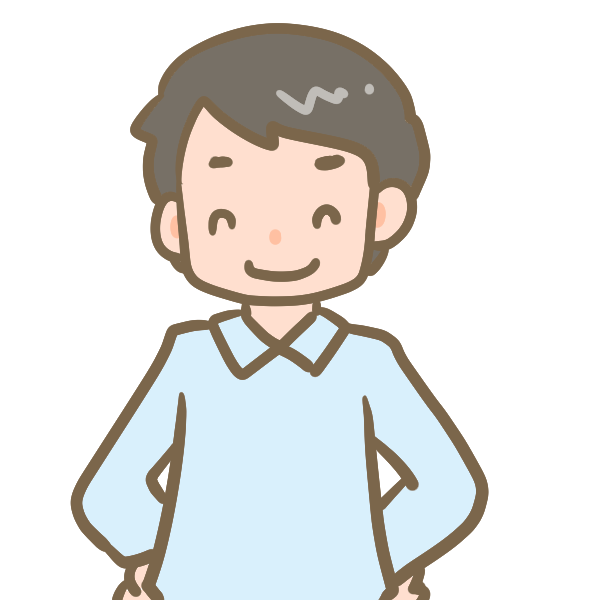
 信号のある交差点でどちらも青を主張したら、どのようにして解決するか
信号のある交差点でどちらも青を主張したら、どのようにして解決するか
警察の事故捜査は供述頼みが現状
警察の事故捜査が事故当事者の記憶による供述頼みで科学的とは必ずしもいえないこと、それを是正すべき立場にある裁判所もそのことに消極的であることが、「科学的交通事故調査」(日本評論社)でわかります。
ただ、私は警察にむしろ同情してしまうところがあります。完全犯罪はありえないとかなどと言われ、期待されているため、事件が起こるたびにその解決を求められる。保険調査でも同様ですが、実際問題として解決できず不明なこともあるはずなのです。
一生懸命捜査したけれど、わからなかった。そういうことがあってもしかたないと思います。それを許さない国民感情。わからんことはわからんでいいのではないでしょうか。神様がやっていることじゃないのですよ。人間がやっていること。それが、「10人の真犯人を逃すとも、1人の無辜を罰するなかれ」の大切さに通じると思います。

事故当事者の証言は信用なきものとして扱え(江守一郎)
また、交通事故工学の第一人者である江守一郎氏は、目撃者の証言があてにならないことをその著書「自動車事故工学」で、以下のように述べられています。
目撃者の証言は多くの場合、信頼性のないものである。その理由は…事故はアッという間に起こり、自動車の衝突時間そのものが人間の反応遅れより短いか、同程度であうからである。したがって、衝突速度や衝突過程などに関する証言は、当事者のものでもよほど注意して聞かなくてはならない。
当事者の多くの場合ほとんど何が起こったのかを覚えていない。当事者が事故後に見た車や建造物の壊れ方から、自分なりに想像するか、または事故後に聞かされた話を総合して、判断しているのであるから、素人の推測の域を出ない。しかも当事者は多かれ少なかれ、自分に有利なように解釈して事故に関する証言をするから、むしろ初めから信用できないものとしてかかったほうが無難であろう。(P151)
「ひとりよがりの哲学」(福田定良著)を読んで
何でこんな話をしてみようと思ったのかというと、以前読んだ本に、これとよく似た場面に出くわしたからです。20日前のわずか30分間の行動を分刻みで要求される場面がそこにありました。その箇所を引用する。
たとえば、彼女は自分にかけられた疑いを解くために、問題になった30分の時間を事務室ですごしていたと主張する。ちなみに、問題になったのは3月19日の午後7時30分から8時までの間であり、尋問が始まったのは、それから20日後の4月8日である。
尋問者は沢崎悦子のアリバイ主張に対して、その30分の間「・・・何をしていたかを逐一時刻を追って、分刻みに説明・・・」するように要求する。こまかいところは本書に譲らねばならないが、警察官の「助言」にしたがって思い出してみても、どうしても15分という時間が残ってしまう。
むろん、この時間も空白のままにしておくわけにはいかない。彼女の方では、自分の無実を主張しつづけているつもりなのだが、尋問にこたえてゆくという形で、次第に両者の関係は、彼女が相手の期待に添うような返事をする関係になってゆく。
(「ひとりよがりの哲学」福田定良著より)
ここのところで、著者は「孤絶した部屋で、一切外界からの情報を絶たれ(逆に、警察側が操作した情報のみをそそぎこまれて)、1日に9時間にも10時間にも及ぶ追及を受けるとき、人の心がいかにもろく弱いものであるかを、われわれは知らなければならない」としています。

この本は、私の好きな哲学者の福田定良が、甲山事件をテーマにして、犯罪者意識を考察した本です。甲山事件というのは、私もちょっと記憶があるだけで、たしかそんな冤罪らしき事件があったようなくらいしか思い出せませんでした。
ここでは甲山事件そのものについて話題にしたいわけではなくて、人間の記憶がいかに移ろいやすくいいかげんなものなのかということ。そして、その移ろいやすくいいかげんな記憶を元に犯罪者かどうかを決めてしまうことの恐ろしさを示す1事例としてとりあげたしだいです。
1日前のことですら私は忘れてしまうことが多いのに、20日前のことですよ。それも分刻みで。何をしていたかを思い出せと追及される。答えられないと、なぜわからないのだと叱責されるです。これが毎日9時間にも10時間にも及ぶのだから、そりゃ、冤罪事件も起こりますよね。
1年以上も前に発生した事故の飲酒調査
私が扱った案件の中に事故から1年以上経ってから依頼を受けたものがありました。飲酒調査です。この手の調査は事故があってから1~2週間ほどでの着手がふつうなのです、これは1年以上経っていました。何考えているだ、アホかと当時の私は思ったものです。
実をいうと、損保がほったらかしにしておいた案件で、契約者が猛烈に抗議した結果、1年経って重い腰をようやくあげたのでした。損保としてはこのまま放置しておくわけにもいかず、車両保険金の請求事案なのですが、支払ってしまおう、そのための理由付け調査ですね。
飲酒疑惑があるが、支払いを正当化するための口実を探すための調査。契約者と面談しましたが、なにしろ事故は1年以上も前に起こったことです。そのときの事故状況は?と聞いても、細部の記憶が失われているだけでなく、自分に都合のいいことが付け加えられているのがふつうです。
さらに、肝心のクルマは修理済みだし、ぶつけた先の店舗も修繕されていた。事故との整合性があるかどうかも調べてこいということでしたが、・・・そんなこと今さら聞いてわかるはずないよ。契約者があきれるだけでなく、聞いているこっちも恥ずかしくなり情けなくなってくるしまつ。もちろん、飲酒していたかどうかなんてわかるはずがありません。
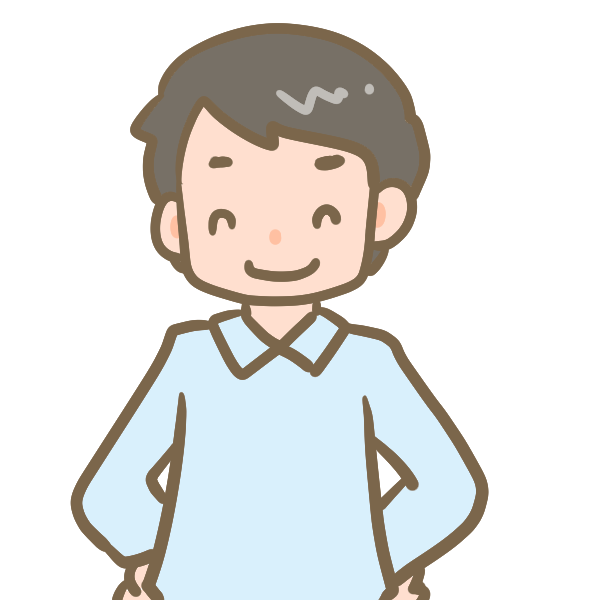
私の知っている調査員の中に、飲酒調査の際に、事故から2週間ほどたってから、15分単位で、事故当日何をしていたのか克明に契約者から聴取しているのがいました。どうだ、すごい調査だろうと報告書を私に見せて、自慢するのがいた。
2週間ならまだ覚えているかもしれないが、それにしても15分単位はいくらなんでもやりすぎじゃないかと、私は思いました。調査している側は、時に調査をされている側の立場に立って、本当にそんな細かいことまで覚えていられるのかと、自問自答してみるべきです。
甲山(カブトヤマ)事件についてもっと知りたい方は以下のサイトが詳しい。
甲山事件:無限回廊

