自賠責後遺障害認定実務上、PTSDもいちおう後遺障害の認定対象として取り上げられています。が、あくまで形だけーーといったらいいすぎかもしれませんが、申し訳程度にとりあげているにすぎません。
実際上は、その入口で締め出されていると言ったほうがいいかと思います。なぜ、そうなのか。認定が困難な理由について詳述しました。
目次
交通事故で子供がPTSDを発症?の相談
子供が交差点の横断歩道を歩いていて、バイクと衝突しました。幸いかすり傷ていどでしたが、それ以来バイクを見ると恐がってしまいます。PTSDなのかもと思ってしまいます。子供の将来を考えてると、PTSDになってしまったら色々大変な事になるのではと思います。
PTSDと認定されたら、保険金請求額の積み増しはどの位になるのか、又どれ位時間がかかるものなのでしょうか。
PTSDは後遺障害ではない?
ネットを見ると、PTSDによる後遺障害の記事がたくさんヒットします。そのため、後遺障害として認定されやすいのかもと、誤解されている方がいます。この相談者の方もその1人のようです。
茶化して言っているのではなくて、自賠責で後遺障害認定されることはほとんどありません。理由はいたってかんたんです。誤解を恐れずにいえば、PTSDを後遺障害と考えていないからです。
後遺障害とは、永続性のあるものです。未来永劫治らないものです。ところが、画像上異常所見もないようなPTSDは、一時的なもの、そのうちに治っちゃうものだろうと考えられているからです。人によっては10年かかるか15年かかるかもしれない。が、結局は治るものだと考えられている。
したがって、自賠責は後遺障害として認めたがらない。例外的に認めるばあいがあったとしても、せいぜい14級です。12級は、宝くじに当たる確率くらいにしか認定されないと思っておいたほうがいいと思います。9級は? これはお題目に挙げてあるだけですね。
すなわち、自賠責上、PTSDは「非器質性精神障害」に分類され、9級(就労可能な職種が相当な程度に制限される)・12級(多少の障害を残す)・14級(軽微な障害を残す)・非該当に分類されますが、ほとんどは非該当なのです。
以上のようにPTSDで後遺障害の認定を受けるというのは相当に難しいことです。というのも、そのための要件がとっても厳しいからです。
後遺障害認定困難な理由その1・外傷体験の激烈さ
その理由のひとつは、外傷体験の激烈さです。主観的に外傷体験が激烈だと思っていても、それだけでは足りません。客観的に外傷体験が激烈でないとダメです。
すなわち、ふつうにだれが考えても命の危険を感じるほどの体験でないとダメだということです。主観と客観の両方が備わっていないとダメですね。問題になるのは客観のほうです。客観的事実があってはじめて事故とPTSDの因果関係が認められる。
相談者の事故の態様は、「バイクと衝突しました。幸い外傷はかすり傷です」。この内容では、後遺障害に認定されることは相当に困難です。スリ傷程度の事故では命の危険を感じることは常識的にはないだろうから、因果関係は否定されてしまいます。
参考のために、後遺障害に認定された裁判例と認定されなかった裁判例をひとつずつ紹介しておきます。どれほどの体験なのかに注意して読んでください。
後遺障害認定が困難な理由その2・症状の発症時期
裁判で認定された例をもう一度確認してください。「被害者は、息子の死亡直後から強い抑鬱状態となりフラッシュバック症状が出現し」と書いてあります。PTSD様の症状が出たのは息子の死亡直後、すなわち事故から2日目です。
この方ご自身が負傷したわけでないためPTSDの症状は事故から2日目と早いのですが、たいていはこんな早くに症状を訴えることはありません。訴えていたとしても、骨折などによる痛みなど他の重い症状にばかり注意がいって、PTSD症状については見逃されることが多いのです。
そのため、事故から半年あるいは1年ほどたって精神科に通院しだし、そこで初めてPTSDと診断される。こういうケースが多いのですが、これだともう後の祭りなのです。
症状はいつから? 記録上確認できるのは精神科に通院しだした半年後あるいは1年後ということになってしまう。半年あるいは1年間も精神科に通院しなかったのだから…ということになって、事故との因果関係がはっきりしないことになり、PTSDでの後遺障害認定ではたいへん不利な事実となってしまいます。
ただこういうことはありえます。精神科の通院はなくても、整形外科で治療をしていて、たまたま診断書やカルテにPTSD様の症状が記載されている場合があります。その場合は、「PTSD様の症状が事故当初から発症していた」との間接証明になります。
後遺障害認定が困難な理由その3・精神科等専門医の治療歴
初医である整形外科主治医が診断書あるいはカルテに「PTSD様の症状あり」と書いてくれていたとしても、それだけではたりません。理由は、整形外科医はPTSDの専門医じゃないからです。
したがって、後でもいいから、専門医にかかることがPTSDによる後遺障害認定の条件になります。専門医の確定診断が必要なのです。
これが自賠責の認定条件です。ああ、なんて厳しいんでしょう。
PTSDの診断基準
PTSD診断基準
診断基準についてはWHOによるものとアメリカ精神医学会によるものとの2つが存在します。いずれも外傷体験の激烈さがその要件になっており、それに続発する各症状の出現がないと認められません。続発する各症状の内容の詳細については、ネットで検索すればすぐに見つかります。
ここでは詳しい説明は省略します。現行のPTSDの診断基準は、こちらで確認できます。
PTSD鑑別診断
それよりも大切なのは他の類似の疾患との比較のほうです。ちょっとしたことでPTSDなんじゃないのかという悪しき風潮があるようなので、その鑑別診断についてあげておきます。
【PTSDではないPTSD症状】
典型的なPTSD症状は認めるものの、臨床的に著しい苦痛または機能の障害を生じるほどの程度でないもの。【急性ストレス障害】
ストレス因子を経験した最初の1か月以内に症状が限定されるもの。【適応障害】
PTSDと同様に、これはストレスに対する反応として生じているが、ストレス因子が十分に強くないか、または反応としての症状が閾値下のもの。【他の精神疾患】
極度のストレス因子への反応には抑うつ障害、不安症、または短期精神病性障害があるが、PTSDの特徴的な徴候を伴っていないもの。【フラッシュバックを引き起こす他の要因】
たとえば、物資使用による知覚変容、頭部外傷、双極性障害、抑うつ障害、または精神病性障害。【詐病】
ストレス因子が強いものでなく、かつ/またはPTSDと診断されることによって経済的もしくはその他の利益が得られる場合にとくに考えられる。
「DSM‐5 精神疾患診断のエッセンス」(P114‐)
PTSD診断のチェックポイント
診断基準そのものよりもそれに該当するかのチェックポイントのほうを理解したほうがわかりやすかったので、そちらのほうをご紹介しておきますね。詳細は「DSM‐5 精神疾患診断のエッセンス」(P115)に書かれているので、そちらで確認してください。
【極度なストレス因子とみなされる条件】
たとえば、予見できる愛する人の喪失、離婚、解雇、放校など人生における大きなストレス因子にすぎないものは除外される。
【症状の重症度】
極度のストレスに直面した後にPTSD様症状になるのはごくふつうにみられること。それだけでは足りず、「症状が重症で、持続性があり、臨床的に著しい苦痛または機能障害を生じていなければならない」。
【期間】
「急性ストレス障害」ストレス因子曝露後3日から1か月以内
「PTSD急性」1~3か月
「PTSD慢性」3か月超
「PTSD発症遅延」6か月を超えての発症
【司法における問題】
PTSDはすべての精神疾患のなかで司法的文脈の中で理解するのが一番困難な分野のひとつ。症状は完全に主観的なものであり、容易に装ったり、誇張したりできる。その一方で、かなり明確な症状が認められるにもかかわらず、PTSDを頑なに否定する人もいる。
現行のDSM-5は、PTSDの罹患範囲を拡張しています。かつてはストレス因子曝露の直接の体験者だけに限定していたのに、この改訂版では、直接の曝露がなくても肉親や友達が体験した暴力的で悲惨な出来事を単に聞いただけでPTSDと診断できるようになりました。
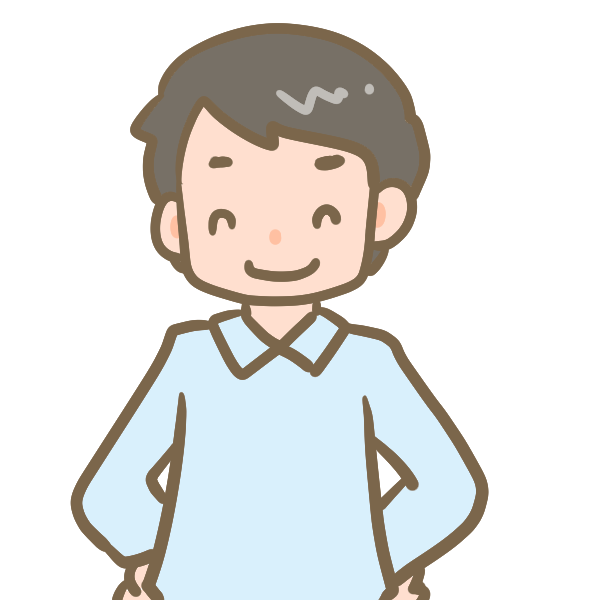
PTSDの過剰診断の問題
DSM-Ⅳの監修者アレン・フランセスは彼の著書「〈正常〉を救え 精神医学を混乱させるDSM-5への警告」で以下のように述べ、警告しております。すなわち、現行のDSM-Ⅴは要件が緩く、PTSDについての過剰診断になりうると危惧されているのです。
DSM-Ⅳに載っている全疾患のなかで、心的外傷後ストレス障害(PTSD)は診断が過小な代表例であると同時に、診断が過剰な代表例でもあるという矛盾した病気になっている。この正反対の誤りはありがちで犯しやすい――私も両方の誤りを犯すので、そのことをよく知っている。
苦しみに黙然と耐えるとき、PTSDは見落とされる。金銭的利益の引き金になるとき、PTSDは過剰に診断される。(P247)
反応が正常と見なせるほど一過性のものなのか、それとも精神疾患と見なせるほど強烈なものなのかどうかは、何によって決まってくるのだろうか。
トラウマの性質と持続期間には多くのものがかかわってくる。ストレスが過酷で、長くつづき、当事者として鮮烈に体験し、無力感を覚えるほど、PTSDになりやすい。
銃撃された人は銃撃を見た人よりリスクが高いし、銃撃を見た人は銃声を遠くから聞いただけの人よりリスクが高い。人間によって故意に与えられた恐怖は――拷問、レイプ、暴行などは――事故や天災より重い症状を引き起こしやすい。
経過も被害者の人となりや背景に左右される。トラウマの前に精神的な問題をかかえていた人ほど、つらい反応が長引きやすい。
それに、トラウマは積み重なる――体験すればするほど、PTSDのリスクは増す。家族、仕事、支援システム、治療は助けになる。飲酒や薬物の使用は事態を大きく悪化させる。
字面でこそPTSDは単純明快だが、現実世界で正確に評価するのはたいてい困難だし、不可能ですらある。定義の最初の部分は――トラウマとなるストレスの性質を定めるのは――たやすい。
日常生活にありがちな問題など及びもつかない、激烈な恐怖をもたらすものでなければならない。レイプ、暴行、車の大破、天災、拷問、戦争、暴力による愛する人の死傷などは――みな条件を満たす。
暴力をともなわない災難は――離婚、失業、破産、失恋はどは――PTSDを引き起こさない。(P248-)
PTSDが認定されづらい背景
PTSDということばは、昔から知られているのではなくて、比較的最近になってからです。その名を世に知らしめたのは中井久夫氏です。中井氏の著書から引用しましょう。
PTSDという障害名は米国の精神医学の診断基準「DSM」の第3版(1980年)に初めて登場して、われわれを驚かせた。それは「不安障害」の一項目であって、「その特徴は極度の(心的)外傷的事件を再体験することであって過剰覚醒症状と外傷と連合している刺激の回避とを伴う」と要約されている。
この障害にはDSMⅢという診断基準の中で大きな例外となっている重大な点が1つある。それは何であろうか。この米国の診断基準は第3版になって初めて世界的に有名になり、1980年代のわが国の精神医学にも1853年のペリー提督のような「診断学的黒船」の衝撃を与えたものであるが、その大原則の1つに「操作的診断」すなわち診断を満たす条件を列記して、全項目のいくつかを満たせば何々障害と診断してよろしいという方式を採って、一切、原因については触れないということがあった。
ところが、PTSDに限り、「心的外傷的事件に続発する」という原因の規定を述べてあるから、明らかに例外である。1994年に出た改訂版DSMⅣでは「急性ストレス反応」が分離されて、例外が2つになった。これはPTSDの急性型であるが、基本的には同じものである。
1つであろうと、2つであろうと、この大きな例外はどういうことを意味するのであろうか。多分こういうことであろう。
精神医学において、従来の精神障害を「内科的疾患」とすれば、心的外傷に続発する障害は「外科的障害」である。こちらのほうは、個人的に耐え忍び、自分の中に抱え、自力で処理されるべきものとされてきた。たとえば肉親・近親者・親友との離別、死別、幼児虐待、性的虐待、犯罪被害、被災、戦争体験、死に至る病の告知を受けること等々である。ところが、そうではなくて、コミュニティの中で支えられ、援助されるべきであると考えなおされてきた。
この最近の世界的な思想的・社会的開眼という大きな文脈の精神医学版がPTSDとなって現れたのである。(P155)
急性ストレス反応との線引きの難しさ
PTSDが認定されづらいことについて、事故との因果関係を中心に説明したとおりですが、さらにその背景として、後遺障害の対象にならない「急性ストレス反応」との境界線引きがむずかしいことです。ネットで調べてみたところ、急性ストレス反応とPTSDの区別について、このような説明をみつけました。
強いストレス因と症状の発現との間に「即座で明らかな時間的関連」が必要とされています。症状の発現が4週間以内で、終息するのも4週間以内とされています。
なお、症状が1ヵ月を超えて持続し、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の基準を満たすような場合には、診断は「急性ストレス反応」から「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」へと変更されます。
教科書的にはこのとおりなのでしょうが、実際は線引きがむずかしいというのが自賠責実務担当者の弁です。すなわち、診断書の症状所見の初診時からの推移をチェックしていると、PTSDと急性ストレス反応の差が判然としない記載をしている事案が大半なのです。教科書的な区別が通用しないのが実態なのです。
なぜそうなのかというと、中井氏によれば、PTSDと急性ストレス反応は本質的に同じものだからです。本質的には同じものをどうして2つの傷病名(PTSDと急性ストレス反応)に分ける必要があったのか。そのことについて、中井氏は同書でこのように説明しています。
通常の心理的メカニズムで解消できるものをPTSR(心的外傷後ストレス反応)としてPTSD(心的外傷後ストレス障害)から区別しているが、本質的に相違はなく、補償の対象になるか否かを決めるために境界線を引いたのであろう。アメリカではPTSDがらみの訴訟がはなはだ多い。(P162)
医学的要請によるものではなくて、政策的要請、もっと露骨にいえば保険会社の注文に応じたということでしょう。
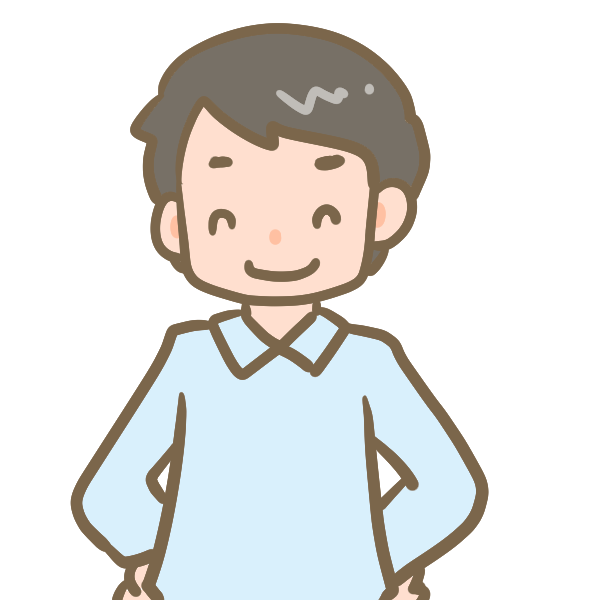
中井氏によれば、この区別は結果論だといっているのです。症状が長引いて1か月以上持続したらPTSD、それ以下だったらASD、治療を要するまでもないものはPTSR、その境界を「正常」だとか「異常」だとかと区別しているのは、医学的説明をつけたいための苦し紛れ、帳尻あわせだということでしょう。
PTSDはだれでもがなりえること
もうひとつ。これまでのPTSDは、「個人的に耐え忍び、自分の中に抱え、自力で処理されるべきものとされてきた。・・・ところが、そうではなくて、コミュニティの中で支えられ、援助されるべき」ものというふうに変わってきたと中井氏は述べられています。日本は社会的な観点からとらえたPTSD認識にまだまだ欠けていることがその背景にあるということです。
このことが、PTSDに対する後遺障害認定実務上の冷淡さ・無理解に現れているのだと、私は、中井氏の他の著書もふくめて示唆されているように感じました。
PTSDを考える上での必読書籍として、中井氏訳の「心的外傷と回復」(ジュディス・L. ハーマン)
という本もあります。
そこでは、事故体験による心的外傷を負ってからかなりの年月が経ち、もう思い出さないかと思っていたころになって、ある小さな刺激を受けたことで突然よみがえり、それを起因としてさまざまな精神的症状が出現する例をいくつも挙げています。
いったん無意識の中に取りこまれた心的外傷の記憶が、ささいなきっかけで、亡霊のようによみがえり、そのため精神的な危機に陥る。
そして、これまでの精神的な病気は、「内科的疾患」として、ある特定の人々のかかるものだと考えられていました。
それが、心的外傷は外傷体験を契機として起こる「外科的障害」のため、PTSDはだれにでも起こりうることになってしまいました。精神医学が、心的外傷を通路にして、いっきに外に向かって開かれてしまったということです。
PTSDは非器質性精神障害のひとつ
自賠責後遺障害認定実務上、PTSDが後遺障害として認定されることがどれほどむずかしいことなのか理解いただけたでしょうか。そうなると、裁判しかないですね。で、裁判の実情についてはあとでとりあげます。
それでも後遺障害として自賠責に認定される方法がないのかというとないわけではありません。もし、お困り方がいらしたら当方にご連絡いただければよろしいかと思います。
PTSDに対する裁判所の考え方
「交通関係訴訟の実務」P148-は、交通事故訴訟をリードする東京地裁民事27部に属する裁判官によって書かれた本ですが、以下のようにPTSDについてかなり厳しい評価を下していますね。
このようにPTSDについて厳しい判断をしているのが裁判所の実情ですが、DSM-5基準と、ICD-10基準を参考にして、以下の4要件を厳格・厳密に適用・運用しているからです。
強烈な外傷体験
再体験症状(フラッシュバック)
回避症状
覚醒亢進症状
PTSDに関する判例
東京地裁平成14年7月17日判決
交通事故はていどの差はあれだれしもストレスを感じる出来事であるが、ストレス症状が、傷害の治癒や時の経過によっても消失せず後遺障害として残存した場合には、傷害慰謝料を超えて賠償の対象となり得るところ、目に見えない後遺障害の判断を客観的に行うためには、今のところ下記基準に依拠せざるを得ない。
外傷性神経症より重度の障害を伴う後遺障害として位置づけられたPTSDの判断にあたっては、DSM-ⅣおよびICD-10の示す①自分または他人が死ぬまたは重傷を負うような外傷的な出来事を体験したこと②外傷的な出来事が継続的に再体験されていること③外傷と関連した刺激を持続的に回避すること⓸持続的な覚醒亢進症状があること――という要件を厳格に適用していく必要があるとした。
それまで緩く後遺障害として認定されていたPTSDが、この判決を契機に門戸を閉ざしたといいほどに要件が厳格適用されるようになったリーディングケースです。上記東京地裁27部の考え方もこの判決を踏襲したものです。
DSM-5に改定されたことによる後遺障害認定の変化
その後、DSM-Ⅳが改定されDSM-5になったことをうけ、「後遺障害等級認定と裁判実務」で下記のように説明されています。
注目すべき変化としては、外傷体験につき、DSM-Ⅳにあった、被災者の驚愕反応の存在が診断要件からはずされた点(ただし、外傷体験の前提となる被災の激烈さについては、ゆるめられてはいない)および被災者自らが受傷ないしは被災体験をした場合だけでなく、近親者の被災の伝聞であっても外傷体験の要件を満たすとされた点である。
後者の点は、伝聞体験でも診断基準を満たす可能性を肯定するものであるが、現実に被災する当事者が「近親者または親しい友人」とされているので、単に衝撃的な事実を見聞きするということではないことに注意すべきである(P208-)。

