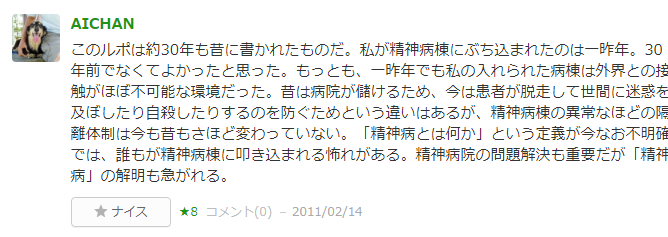目次
高次脳機能障害は「頭が悪くなる」病気なのか
父が脳梗塞を起こし、高次脳機能障害で苦しんでいることは以前書いた。ところで、父の主治医である脳神経外科医は、高次脳機能障害を、「わかりやすく言えば頭が悪くなる病気」だと入院当初に私に説明した。それってたぶん誤解ではないだろうか。頭が悪くなるのは認知症であって、高次脳機能障害ではない。高次脳機能障害になったからといって必ずしも頭が悪くなるわけではないからだ。つまり、認知症と高次脳機能障害との決定的な違いは、「自分がだれだか知っているかどうか」である。客観的に自分を見つめられ、自分の行動に自覚があるかどうかである。自覚があるほうが高次脳機能障害、ないのが認知症である。たとえばイヌの絵をみてネコと言ったり、ある質問に対して意味不明の言葉(ジャルゴン)を発したりすることが高次脳機能障害者によくみられる。はたからみると理解不能でイカレタとしかみえないだろう。しかし、彼らは質問の意味・意図がわかっているが、それをうまく表現できないだけである。だから内面での理解ができているのにもかかわらず、それを外界にうまく表現できない。自分がおかしな発言をしていることがわかっているのに修正できないため苦しむ。質問の意味・意図自体がわからない認知症とはこの点で決定的に違うのだ。
高次脳機能障害の、後遺障害認定上の問題点
高齢者の場合の高次脳機能障害の後遺障害認定で争いになりやすいことのひとつは、高齢者だと事故前から認知症を患っている場合があったり、事故後の入院が長引けば認知症になりやすいことから、発現している症状のうちの、どこまでが認知症によるもので、どこからが高次脳機能障害によるものかとか、事故後に発症した認知症がどこまで事故と関わっているのかである。つまり、事故との因果関係や賠償の範囲、素因減額の問題である。ところが、脳神経外科医でもその区別ができず、こんな程度の認識なのである。高次脳機能障害の患者に日常的に接する看護士も、「なになにでちゅか」などとお子様言葉で話しかけることもあるらしいから、これはこの医者がたまたま無知だったわけではない。医療界全体においてさえ高次脳機能障害の認知度はこのていどなのである。
高次脳機能障害者は精神に問題があるのか
このように高次脳機能障害と認知症とがうまく区別されていないために、実は困った問題が発生している。行為能力に制限が課されている問題である。行為能力に欠けているあるいは不十分だとして法律行為をすることに制限を課している問題である。その典型例はいわゆる成年後見の問題である。それにかかわる民事上の規定について、「家族法 二宮周平著」ではこのように記載されている。
[amazonjs asin=”4883841979″ locale=”JP” title=”家族法 (新法学ライブラリ)”](法定後見について)家庭裁判所の判断によって成年後見の開始が決められる制度である。本人の判断能力の程度に応じて①後見類型②保佐類型③補助類型の3類型で対応する。これらの内容は法律で定められており、変更できない。本人、配偶者、4親等内の親族、検察官(民7、11、15Ⅰ)、市区町村長などが、本人の能力に対応して、3つの類型のどれかの開始を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所は、①②では、本人の意思を確認し③では、本人以外の申立ての場合に、本人の同意を要件とする(15Ⅱ)ことによって、本人の意思を尊重しながら、①②では、精神鑑定を行い、③では、医師の診断結果を聴いて、開始するかどうかを決定する。(P242)
民法の条文をここで再確認してほしい。
被成年後見人や被保佐人、被補助人についての要件が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」とか、「事理を弁識する能力が著しく不十分である」とか、「事理を弁識する能力が不十分である」とかとなっており、この規定はあいまいさを含む。そのあいまいさを厳密にするために医者を介在させて「精神鑑定」あるいは「診断」行為をすることで救おうとしている(注)。
DSMでは「持続的」であることを要求している
DSM(アメリカ精神医学会で出版された精神障害の診断と統計マニュアルのこと)では精神障害は「持続的」であることで判断する。つまり、先の要件である「事理弁識能力が欠けるとか不十分」とかは、精神科医が判定できることではないのだ。まして、診断で精神科医でもない主治医に判定させるべきものでもない。
DSMⅣの編集を担当したアレン・フランセスはその著書である「〈正常〉を救え 精神医学を混乱させるDSM-5への警告」で、また、ジョエル・パリスは彼の新著「現代精神医学を迷路に追い込んだ過剰診断 -人生のあらゆる不幸に診断名をつけるDSMの罪」で何でもかんでも精神異常に過剰診断してしまう現在の風潮に対して警告を発している。
[amazonjs asin=”4062185512″ locale=”JP” title=”〈正常〉を救え 精神医学を混乱させるDSM-5への警告”][amazonjs asin=”4791109589″ locale=”JP” title=”現代精神医学を迷路に追い込んだ過剰診断 -人生のあらゆる不幸に診断名をつけるDSMの罪”]
レイプ犯は精神が異常なのではなくて、倫理に問題があるのだ
たとえば、レイプ犯について精神異常者にくくろうとする風潮が日本でもある。レイプ犯を「反社会性人格障害」などとして精神異常者にしたてあげて、責任は問えないと弁護する風潮などがそうである。しかし、アレン・フランセスは、性的衝動を持つことは病気でないとしている。性暴力とは、いやがる相手に性行為を強制することで、倫理に反する犯罪であるが、精神をやんでいたための行為ではない。そして、米国精神医学会もDSMにそのような診断名を設けることを一貫して、却下してきたと述べている。その箇所を引用する。
レイプを精神疾患と見なすのは常識に反するし、古くからの法律の前例にも反する。レイプはつねに犯罪として扱われ、けっして病気として扱われなかった。聖書でもそうなっている。ずっと古いハンムラビ法典でもそうなっているし、それどころかこれまでに編纂されたあらゆる法典でもそうなっている。・・・いまだかつてレイプが病気として法的に認められたことはないし、レイプ犯の拘禁が刑罰ではなく精神医学に基づいたこともない。
レイプ犯は悪人にほかならず、精神病を患っている者はごくまれである。レイプ犯に精神疾患を正当な理由として使わせるべきではないが、レイプを精神病院に入院させる正当な理由にするべきでもない。レイプ犯には非常に長い刑を言いわたして街をうろつかせないようにするべきであり、法律の抜け道を作って精神病院に強制収容するべきでない。刑期を終えたら、ほかのありふれた犯罪者と同じように、釈放しなくてはならない。
私の懸念は、レイプ犯に少しでも同情を覚えているからではない。レイプ犯を不公正に扱えば、坂を転がり落ちるようにしてもっと広範囲にわたる憲法の地位低下がもたらされ、法の適正手続の神聖な価値や市民の自由の擁護が尊重されなくなるのでないかと、私は危惧している。他国の恐ろしい事実がわれわれへの警告になるはずだ。一部の国では、政治的な対立や経済的な不満や個人の差異を押さえこむために、刑罰制度が精神医学を危険なまでに乱用している。面倒なレイプ犯に対処するために憲法の原則を危うくするような法制度は、いずれはさらに進んで、面倒な政治的目標や宗教的信念や性的嗜好を持った人々に対しても精神医学を用いるようになるかもしれない。
オーストリアの作家ローベルト・ムージルが70年前にこう指摘している。
「医学の天使が弁護士の主張に耳を傾けすぎたら、みずからの使命をしょっちゅう忘れてしまうことだろう。そのとき医学の天使は音を立てて羽をたたみ、法廷の天使の補欠のように法廷でふるまうだろう」(P260-)
弁護人や裁判官は安易に精神異常を持ち出すべきではない
そういえばつい最近も法廷で変な議論が戦わされたことがあった。そのことを記事にしていたので、ここで再録してみよう。
名大の元女子学生の殺人事件のことが過日の新聞記事に載っていた。
弁護側は冒頭陳述で「発達障害の影響で善悪の判断ができなかったことに加え、双極性障害(そううつ病)のそう状態で行動をコントロールできなかった」と強調。(日刊スポーツ)
日刊スポーツの報道だからどこまで信用していいのかわからない。が、弁護士のこの声明には、腰が抜けるほど私はびっくりしました。交通事故ではあまり聞いたことがありませんが、犯罪がらみで、発達障害はよく話題にされます。発達障害というのは精神的な不調を抱えていれば、だれでも発達障害に認定されるほど相当にあいまいな広い概念なのに(注)、それを理由にして善悪の判断ができないは、いくらなんでも誇張が過ぎるでしょう。加えて、双極性障害で、「そう」になったから行動のコントロールができず、殺人まで犯す??? 明らかな「過剰診断」の例です。
躁うつ病のキーワードは「後悔」である。うつ状態のときは「取り返しがつかない」(木村敏)と悔やみ(土居健郎)、躁状態のときは「なんとか取り返し、埋め合わせ、つぐないをつけよう」とがんばる。(P154)
[amazonjs asin=”4260333259″ locale=”JP” title=”看護のための精神医学 第2版”]
躁うつ病のキーワードは「後悔」です。「後悔」は内方向に向かうエネルギーです。人を殺すような、外に向けた反社会的な行動に出るわけではありません。そもそも、発達障害で「そう」になるのでしょうか???こんな声明をみるたびに、発達障害で苦しんでいる方にどれほどの迷惑がかかり、差別を助長するのだろうかと、私はゆううつになります。
弁護人や裁判官は、行為者に責任能力がないと結論付けのための理由に、安易に精神異常を持ち出すべきではない。裁判官の責任で、犯人の社会的背景や知的能力障害や認知障害のレベルにもとづいて、慎重に判断すべきである。
ルポ・精神病棟
私が大学生だったころ、友人の下宿先で夜遅くまで話し込んでいたときのことだ。深夜のそのとき、玄関ドアをノックする音。と同時に、「助けてください。匿ってください」という若い男性の嘆願する弱々しい声が聞こえた。その後すぐに、「おーい、バカ。すぐに出て来い。逃げようとしても無駄だ」という男性の暴力的な荒々しい声が聞こえた。そうか、ここは、あの有名な精神病院の近くだ。そこを逃げ出した患者だったのだ。友人は、「匿うことはできません」と、入室を拒否した。
その当時、私は朝日新聞記者がアル中を装って精神病院に潜入取材した大熊一夫の「ルポ・精神病棟」くらいは読んでいた。この本を読んで、精神異常にかんたんにされてしまうことを知った。だから、内心「匿うべきかも・・・」と思ったことを思い出す。どう考えても、嘆願する若い男性のほうが「正常」で、暴力的に怒鳴りつけている看護士(?)のほうが「異常」に思えたからだ。
[amazonjs asin=”4022602449″ locale=”JP” title=”ルポ・精神病棟 (朝日文庫 お 2-1)”]
同書を見た方の「読書メーター」がたいへん参考になる。