休車損害とは
休車損とは
休車損害とは、交通事故でクルマが全損したときは次の車を購入するまでの買替期間中、クルマが分損したときは、そのクルマが直るまでの修理期間中、そのクルマが使えなくなるために発生する逸失利益のことです。
代車使用料=休車損
仮に、その間、代車を使った場合はその費用を補填すれば足ります。しかし、代車を利用することが不可能だったり困難だったりした場合、自分のところで遊んでいるクルマ、すなわち遊休車を使った場合や、自社の他のクルマをやりくりした結果、損害を未然に防いだ場合は、原則として休車損害は発生しないこととされています。
遊休車があると休車損は発生しない
遊休車があると休車損は発生しないとされています。有休車の有無については「貨物自動車運送事業営業報告書」の「延実働車両数/延実在車両数」による実働率や、保有車両数、ドライバー数などから、遊休車の存在の有無について推定する方法があります。

遊休車の有無の推定方法で注意すべきこと
遊休車の存在の有無を推定する場合に注意すべきことは、遊休車が存在するかのように見えても、車検・定期点検中で遊休車を使っているため実際の業務に使えない場合があることです。あるいは、他営業所に遊休車があるが、実際問題として回送に時間や費用がかかりすぎる場合があることです。あるいは、遊休車があるものの、それを運転するドライバーの手配が困難な場合もあります。
そんな場合でも形式的に遊休車があるからという理由で休車損害は発生しないなどと結論してしまうなら、運送会社に非常に酷な結果になります。
休車損は緑ナンバーだけに限定されない
また、損保が休車損害を否定する事由に、被害車両が営業車(緑ナンバー)でないこと、すなわち、自家用車であったり、いわゆる白トラ・白タクであった場合は休車損害を否定することがよくあります。
しかし、裁判所は自家用車だからという理由だけで休車損害を否定していませんし、白トラ・白タクについても、それだけの理由で休車損害を否定していません。
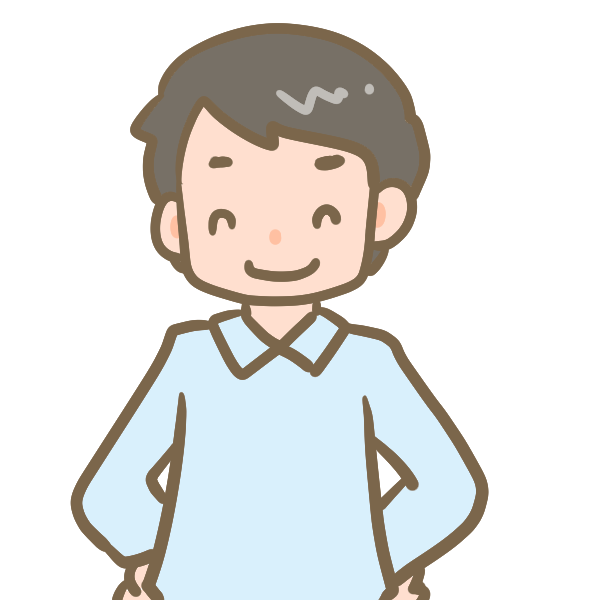
 休車損害を請求できるのは緑ナンバーだけなのか
休車損害を請求できるのは緑ナンバーだけなのか
なお、乗合バスとか貸切バスなどは、「予備車を用意することが条件」になっているので、繁忙期をのぞいて休車損害の対象になりません。
休車損と過失割合
休車損は過失があると発生しないなどと損保は言います。これは明白なウソです。休車損は過失ゼロの場合だけでなくて、過失があっても当然に請求できます。
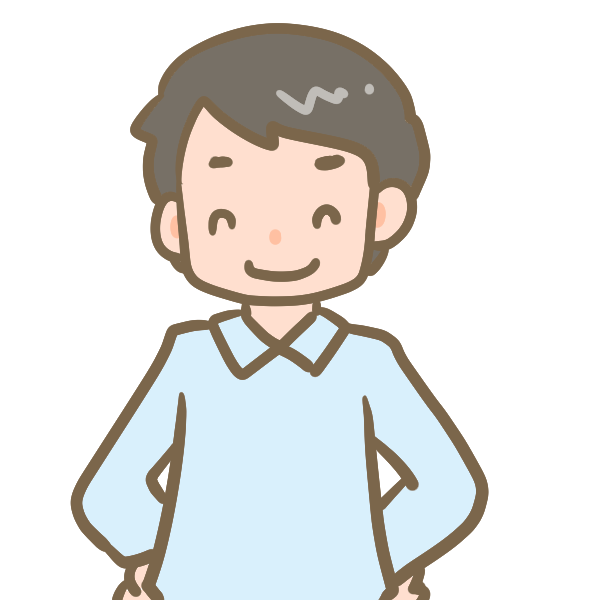
 過失があると、代車費用も買替諸費用も評価損も休車損も認めたがらないわけ
過失があると、代車費用も買替諸費用も評価損も休車損も認めたがらないわけ
休車損害の算定方法
被害車両という個別から算定するか、全体から算定するか
休車損算定の方法ですが、考え方としては2通りあります。
(1)季節変動が激しい場合は1年間という長期間を対象にすることもありますが、被害車両の事故前1か月間あるいは3か月間などある一定の期間を決めて、その間の売上から変動経費を控除し1日あたりの収入を算定する方法。
(2)事業体全体の売上から全変動経費を控除し、保有台数で除して1日1車あたりの休車損害を算定する方法。
(1)は被害車両そのものを対象にして休車損を算定する。(2)は、ざっくりとした計算方法です。細かいことはいちいち気にしない。ただそれができる場合の条件があって、被害車両と他の全車両が概ね同タイプ・同用途の場合に限られることです。
(1)の方法が一般的です。(2)は細かいことを抜きにして大枠で算定できるという利点があり計算も楽ですが、大きな事業体だといろいろな車種が混在しているため、(2)の算定方法はふつう使いにくいかと思います。
休車損害の算定式
それぞれの算定式です。
(1)(被害車両の1日あたりの売上-変動経費)×必要な休車期間
(2)(純利益+営業費-変動経費)÷保有台数×必要な休車期間
変動費と固定費
ここでいう「変動経費」とは、事故により出費を免れた費用のことです。一番分かりやすい例は、ガソリン代ですね。クルマが使えるばあいは燃料であるガソリンが必要ですが、クルマが使えないばあいは必要ありません。
対して「固定費」とは、事故があろうがなかろうが、事故とは無関係に必要な経費のことです。
以下は、変動費に当たるものが何で、固定費に当たるものが何かを書きました。
たとえば、「固定経費」にあたるものとして「減価償却費」をあげましたが、これは分損の場合、すなわち継続的使用が前提になる場合に当てはまるものです。
しかし、全損の場合だと、被害車両は事故により経済的価値を喪失してしまうわけだから、固定費ではなく変動経費扱いになります。自動車保険料などもそうですね。
何が変動経費で何が固定経費かのメルクマールは、あくまで「事故により出費を免れる」かどうかです。
注意すべきは人件費である
ここで特に問題になるのが人件費の扱いです。損保は人件費について変動経費扱いにして、休車損害の対象にふつうしません。
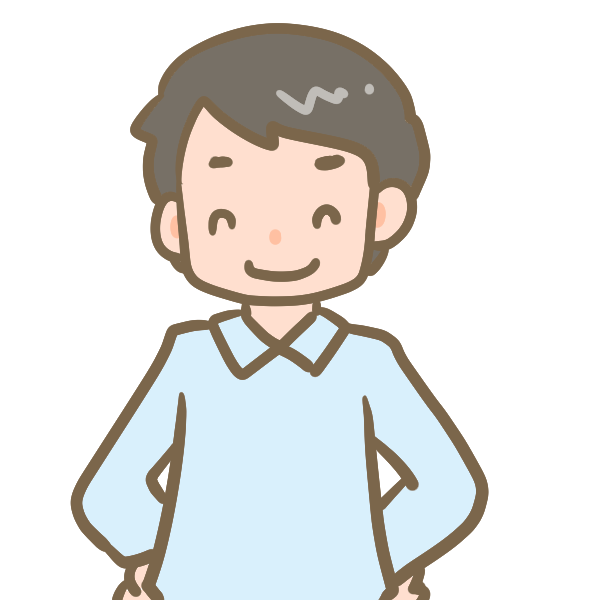
たしかに、アルバイトドライバーの場合は休車期間中休んでもらえばその間の給与支給義務が発生しないのだから、「事故により出費を免れた費用」にあたり変動費といえます。
しかし、正社員の場合はそうはいかないでしょう。クルマが使えないからといって給与を支払わなくていいということにはならないからです。したがって、正社員ドライバーの固定給与部分については固定費にあたり、休車損害の支払い項目に算入されるのです。
ただし、実際によくあるのは、クルマが使えない期間、ドライバーでなくて荷物積みやドライバー助手など他の仕事に回ることが多いのです。その場合は、会社は他の業務をやらせることで利益を得ていますから、その利益分を休車損の対象から除外しないといけません。(なお、後述の札幌地裁平成11年8月23日判決参照)
それと、ドライバーが事故で怪我をして仕事につけない場合は、労災事故になったり、休業補償の対象になったりするので、別異の扱いになることにも注意してほしい。
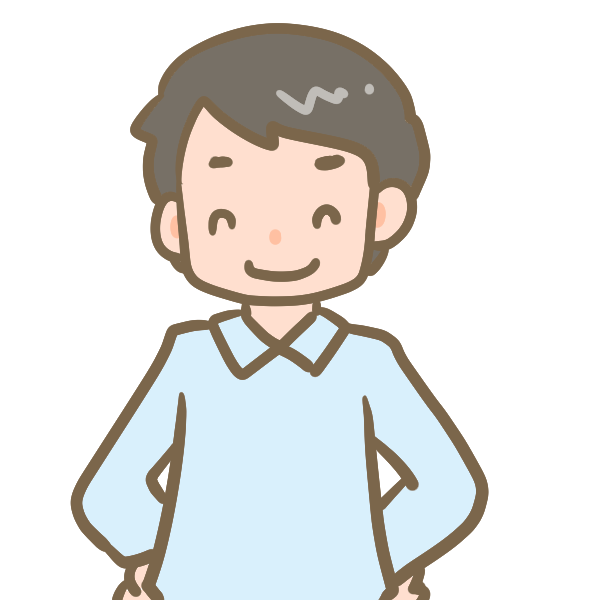
 休車損における人件費の扱われ方
休車損における人件費の扱われ方
休車期間
休車期間は、妥当な修理期間(分損の場合)もしくは妥当な買替期間(全損の場合)ということになるのですが(修理期間は2週間、買替期間は1か月というのが通常)、これも紛糾の種になりやすいです。
よくあるケースとして、損保は、示談交渉で長引いた期間や損保への事故通知が遅れた期間などは休車期間に算入しません。事故通知の遅れは運送会社の責任だからこれは仕方がありませんが、示談交渉により長引いた期間については、損保側に原因がある場合だってあるわけだし、その場合、裁判所も休車期間に含めているので、どうして長引いたのかその経過について細かく記録をとることはぜひ必要です。
さらに、被害車両が特殊車両だった場合に、修理のための部品調達に時間を要したり、買替に時間を要したりする場合があります。これも、どうしてそうなるのかの立証責任はあくまで運送会社側にあるので、普段から資料による裏づけをしておく習慣作りが必要ですね。
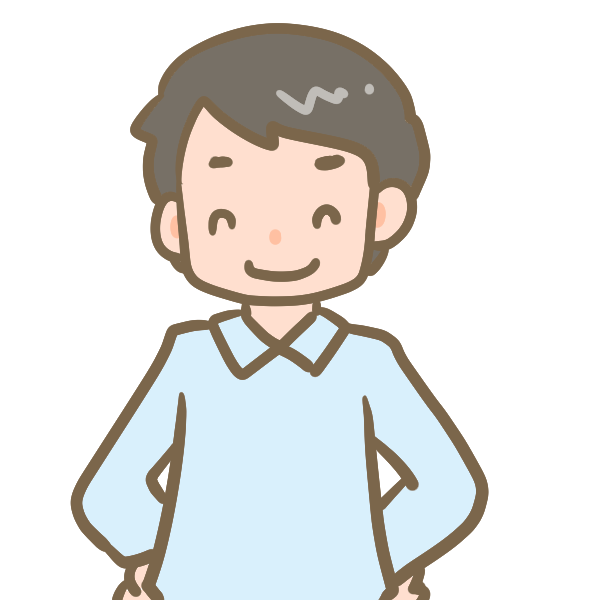
 休車損害を請求する際に必要な資料とは?
休車損害を請求する際に必要な資料とは?
休車損害が発生しない場合
休車損を請求する側に立証責任があること
休車損害を請求する場合にもうひとつ注意を要することがあります。これまでは休車損害が発生していることを前提に話をしてきました。しかし、ばあいによっては発生しているように見えて実は休車損害がまったく発生していないばあいがあります。
以下の例を参考に説明したい。
自分の過失で営業ナンバーのトレーラーと事故を起こしました。修理代は払い終わったのですが、休車補償を請求されています。相手が送ってきた書類は『休車損害請求書』なる手書きの紙です。その紙には事故を起こす前の3か月間の運賃収入や人件費、燃料代などが計算して日割りの料金を出してきています。それに休みなしで計算されているのです。
手書きの資料で相手の自己申告で膨大な金額を請求されていて困っています。
休車損害で注意すべきことは、まず休車損害がそもそも発生しているかどうかです。発生していなければ貴方に支払い義務がないので、相手が何を言ってこようと、それだけなら無視すればいいだけです。
では、どういう場合に休車損害が発生しないのかというと、事故後、遊休車や社内の実稼動車を使用した結果、事故後に発生するであろう休車による損害を防いだ場合です。つまり、実際の損害が発生していないのだから、貴方に支払う義務がないという理屈です。
そして、ここが肝心なのだが、遊休車がなかったこと、あるいは社内の実稼動車を使用した場合であってもそれでも損害が発生したことを相手側が立証しなければならないことです(判例の多くがこの見解)。相手運送会社に立証責任があるのはそのための立証書類を相手が持っているからなので当たり前のことです。あなたがそのことを証明する手立てなどないのですから、相手に立証しろと求めてください。
遊休車の存在を肯定し、休車損を否定した裁判例と、遊休車の存在を肯定したが、休車損を容認した裁判例
遊休車の存在を肯定し、休車損を否定した事例です。19台の事業用自動車を保有、ドライバー数は16。事故前年の4月1日~翌年3月31日までの延実在車両数は6935台、延実働車両数は4636台。実働率は4636/6935=0.668。「事故によって、特定の営業用車両を使用することができない状態になった場合にも、遊休車等が存在し、現に、これを活用して営業収益を上げることが可能な場合には、被害者においても、信義則上、損害の拡大を防止すべき義務がある。したがって、遊休車等が存在し、これを活用することによって、事故車両を運行していれば得られるであろう利益を確保できた場合には、原則として、上記利益分については、休車損害として賠償を求めることはできないというべきである。そして、遊休車の存在については、加害者側において立証することは事実上不可能であるから、これが存在しなかったことについての立証責任は、被害者(原告)が負担すると解するのが相当である」
もうひとつ。以下の判例は、遊休車があるにもかかわらず、被害者は、必ずしも遊休車を使用して損害発生を防止すべき義務はないとして、休車損害を認めた事例です。だだし、少数派に属します。
「被告は、休車期間中に遊休車の存在がなかったことを立証する必要があると主張するが、遊休車が多数存在し、容易にやりくりをして損害発生を妨げる場合でなければ、被害者である原告に必ずしも、遊休車を使用して損害発生を防止すべき義務はない。そして、原告が、本件事故当時、原告車両を含め7台を保有していたが代替車両はなかったと主張しており、原告が、原告車両に代わる新車を購入することもできないでいる状態からすると、遊休車を利用して、容易に配車をし、業務に支障がでないようにできる状態とは認められない(弁論の全趣旨)。したがって、原告には、上記休車損害を認めることができる」
書類の信頼度と裏付け
もうひとつの質問である相手より提出されている手書きの書類についてですが、実物を見ていないので断定はできないものの、本来なら提出書類はかなりの分量になるはずです。
質問をみるかぎり手書きの紙面を2、3枚提出してきたという感じですね。もしそうであるなら、一切無視してかまいません。その書類に記載されている数値が正しいかどうか、その記載の基になった資料、すなわち、運輸局への提出書類や確定申告書、運行日誌などを要求し、どうしてその額になったのか計算式も求めるべきです。
さらに、休車損害の算定対象期間が事故前3か月になっていますが、その3か月間だけ売り上げが多いという場合もありえますから、3か月が平均値を示すもので妥当かどうかについても、相手に書面で立証させてください。
休車損害が発生しているかどうかについては、通常は、貨物自動車運送事業実績報告書から当該事業の車両実働率【延実働車両数/延実在車両数】を把握し、その車両実働率と当該車種の平均値を比較して、遊休車数を考慮にいれ推定します。
当該事業の実働率が平均値より高い場合は休車損害が発生している蓋然性が高いと言われています。場合によっては、保有車両の内訳、そのうち事故車との代替可能の車の数、代替可能遊休車数、ドライバー数を把握して休車損害が発生しているかどうかを推定します。大手運送会社だと、事故車の営業所だけでなく、近傍の営業所の状況も把握する必要があります。
稼働率から休車損害の額を求めるのはふつうないだろう
「遊休車の稼働率は休車損害に反映する」というワード検索で来られた方にお答えします。たとえば実稼働率が80%だった場合、過失相殺の考え方を参考にして、80%認めるという算定をしていた某損保査定者がいました。
示談段階だから被害者がそういう考えを受け入れるなら問題はないと思います。しかし、そのような算定をはじめてみました。裁判でも、そのような算定をした例がないのではないでしょうか。私の限られた範囲なので絶対とはいいませんが、少なくともオーソドックスな考え方でないことは間違いありません。ていうか、相当に無理のある考え方じゃないかと私は思います。
休車損の裁判例
大阪地裁平成5年1月29日
大型貨物自動車が修理のために使用できず、修理期間中に運送を外部に委託した場合につき、委託運送費用から通行料、燃料費等を控除した20万円を休車損と認めた。
神戸地裁平成10年5月21日判決
1日あたり4万4100円の収入を計上する残土運搬車について、経費率が不明であることから民訴法248条(注)に基づいて、1日あたりの利益を2万5000円とし、52万5000円の休車損を認めた。
(注)「第248条損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」
大阪地裁平成10年12月17日判決
貸切大型バスにつき、大型バス協会の運送実情による貸切大型バス一両あたりの1か月の運行収入197万7517円から、当該車両の1か月分の経費74万9787円を引いて1日あたりの利益を4万0924円と算出し、17日分を休車損と認め、遊休車を有していても当該事故車両と同格の遊休車が多数存在しこれを代替することが容易にできる場合を除き、所有者に遊休車を利用してやりくりすべき義務を負わせるべきでない。
札幌地裁平成11年8月23日判決
トラクターにつき、被害車両を専属的に運転している運転手が遊休車がないため別の車両の助手として形だけの業務をしている場合の人件費は、休車中も支払いを免れない性質の経費と評価できるとして、売上高から控除すべきでないとした。
京都地裁平成12年11月9日判決
大型観光バスにつき、稼働状況および運賃収入は季節による変動があることが容易に予測できるとして、休車時期の前年同期の稼働実績に基づいて、1日あたりの運賃収入を算定した。
神戸地裁平成14年7月18日判決
大型貨物自動車であること、過失割合が争点になったので現物保存のため当初は修理を見合わせていたこと、話し合いが不調に終わったため修理に出したところ、当初の予想とは違ってエンジン関係にも大分損傷があることがわかったので廃車にしたことから、92日間の休車期間が不当に長すぎるとはいえないとした。
名古屋地裁平成15年5月16日判決
被害車両が科学的検証のため事故から16日間警察署に留置された事案について、当該期間は公益的見地から国民の義務とされているものだから休車期間に含めるべきではないという加害者側の主張を排斥し、当該期間を含めた修理完了までの95日間を休車期間と認めた。
名古屋地裁平成15年5月16日判決(上の判決日と同じ日だが別判決)
営業用普通貨物車につき、代替車搬入までの49日分80万円を請求した事案において、被害者が取引先からの依頼を断ったことはなく、3台の車両と4人の熟練した従業員により本件事故前と同程度の売上を確保していたが、それは被害者の営業努力による面も大きいとして、上記49日間について、被害車の粗利益の30%に相当する23万7008円の休車損を認めた。
東京地裁平成18年8月28日判決
運送会社の大型貨物車につき、車両が稼働できなかったことによる逸失利益から、車両の運転手が稼働できなかったことにより支払いを免れた休日手当、出張手当、調整手当、時間外手当を差し引いて休車損を算定。
東京地裁平成21年7月14日判決
被害車両(4㌧ロングトラック)につき、全国展開する引越運送業者であっても、実質的には支社ごとの独立採算制を採用し、配車も支社単位で行われている場合、他支社の遊休車を使用して配車調整をすべきとはいえず、休車損はあるが、事故前の稼働率や利益状況が年度や繁閑の時期によって必ずしも同様ではなかったこと等から、民訴法248条の趣旨も含め、休車損の日額を2万3000円としたうえで、時価額内で修理が可能な業者を探していたため入庫が遅れた期間を除いた事故後23日間を修理着手までの相当期間として、修理期間45日間と合計した68日分156万円余りを認めた。
大阪地裁平成22年7月29日判決
普通貨物自動車につき、1日あたりの利益は、当該車両の売上高から変動経費のみを控除して固定経費は控除せずに3万8000円とし、休車相当期間は、注文から納車までの3か月程度と新車購入決断までの検討期間1か月程度の合計4か月(120日)として456万円をみとめた。

