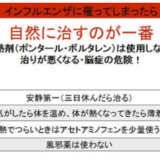裁判員裁判とは
裁判員裁判のことについては私は詳しくは知らなかったので、ああだ・こうだ言うまえに、ちょっと調べてみた。
裁判員裁判とは、
一般市民の裁判への直接的な参加を認めるもので、重大な刑事事件(法定刑に死刑・無期刑が含まれる罪の事件等)について、事件ごとに有権者のなかからくじで裁判員を選出し、原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と一緒に有罪・無罪の決定と量刑を行う、というものである。
この場合の評決は「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数による」とされている(裁判員法67条)。つまり、裁判官3・裁判員6の合議体の場合、過半数は5であるが、そのなかには、必ず、少なくとも1人以上の裁判官が含まれていなければならない、ということである。(P317-318)
[amazonjs asin=”4535521514″ locale=”JP” title=”憲法学教室 第3版”]裁判員制度は、市民参加による裁判の民主化という点で、大いに意義を認めることができる。とりわけ、官僚化した日本の職業裁判官の権威主義的硬直さは、ときとして、浮き世の常識から離れた裁判を生み出しており、ここに素人の目を入れて事件をみれば、多角的な見方ができて裁判の硬直化が避けられる、という期待もできよう。しかし、どんな制度も、すべてよし、とはいかない。裁判員制度についても、職業的な訓練をうけていない素人の判断が感情・恣意に流され誤った結論を導き出すことにならないか、という危惧は、とうぜんありうるところである。犯罪に対して「厳罰」を求める社会的圧力が強いところでは、その危険はいっそう大きくなろう。(P319-320)。(以上「憲法学教室」浦部法穂著)
市民感覚とは何か
似たような制度として陪審制がある。両制度の違いは今回記事にするまで知らなかったが、両制度には共通する面がある。市民の司法参加である。すなわち、仕事も生い立ちも学歴も違うさまざまな階層の人たち、年齢だって違っていて、それこそ、無名のおっちゃんやおばちゃん、兄さん、姉さん、爺さん、婆さん、そういった市民が裁判にかかわることで、裁判の権力性への一つの対向原理をうち立てること、裁判の民主化に資することが目的であって、そういう目的からいわば市民感覚を裁判にとりいれようとしたものである。ところがこの「市民感覚」というのがくせものだ。都合のいいように解釈されて、一人歩きしているように、私は思うのだ。
「市民感覚」とは、ヤラレタカラ・ヤリカエセというのとも違うし、疑わしいだけで被告人を死刑や重罰にしていいということとももちろん違うだろ。法律上それは許されないだけでなく、市民感覚としてもそういうのは許されない。根拠もなしに、感覚で結論を出していいということにはならないのだ。
えらそうなことを書いたけれど、実をいうと、裁判員裁判の実際については私は何も知らない。だから「市民感覚」といわれても、実際に裁判を傍聴したことさえないのだから、よくわからない。しかし、陪審制を描いた「12人の怒れる男」という映画なら観たことがある。たいへんすばらしい映画だった。陪審制の理想像が描かれている傑作だと言われている。裁判にとりいれるべき「市民感覚」がどういうものなのか。その映画で具体的にどんなふうに描かれているのか。そのことを知るために、この映画をもう1回観てみたくなった。そして、この記事を書くためにさらにもう1回観た。つまり、3回観たことになる。
12人の怒れる男
この映画で扱われているのは、スラム街に住む犯罪歴のある少年の父親殺し事件である。事件の概要はこうである。
少年にはアリバイがなく、凶器であるナイフも、少年の自宅で父親の胸に突き刺さったまま発見されている。事件現場から少年の「殺してやる」という叫び声と殺人の直後に現場から逃走する少年を見たという階下に住む老人の目撃者がいるし、殺人そのものを目撃したとされる隣家の女性証人もいる。このような、もう、圧倒的に不利な状況下で、ヘンリーフォンダ演じる8番陪審員は、他の11人の陪審員が有罪だとした評決に、1人だけ反対票を投じることから陪審の審議が始まる。
ある法廷で父親を殺したとされるスラム育ちで犯罪歴のある少年の裁判が行われた。希望が持てそうもない表情の少年。

目撃者による証言も終わり、今回の陪審のために召集された、お互いに顔も名前も知らない12人の陪審員たちは、最終審議で法廷から陪審室に移る。けだるく暑いニューヨークの真夏日。クーラーもないため、「早いとこ片付けようぜ。ヤンキーズ戦のナイターにいくつもりなんだ」と、早く終わらないかと陪審が始まるのを待つ陪審員もいれば、「殺人事件でよかった。傷害や窃盗じゃ退屈だからね」と、興味本位の陪審員もいる。そして、ようやく陪審が始まった。
陪審員1番。「どう採決するか私がルール作るわけじゃないが、まずは話し合って採決するのも一案だと思うし、さっさと採決するのもいい」と言い出す。ナイターを見に行きたい陪審員が「採決だけだとすぐに帰れるかもしれん」と言い出し、反対もないため採決ということになる。
「これは第一級殺人です。全員一致で少年が有罪とする場合、少年は電気椅子送りになる。それじゃ、有罪だと思う人は手をあげて」。11人。「では無罪だと思う人?」。すると、8番陪審員が手をあげ無罪を主張する。

みな一致で有罪だと思っていた他の陪審員たちは驚き、「やれやれ、いつもこういう奴が1人いる」とため息を漏らす陪審員たち。「あきれたね、本気で無罪だと思っているのか」と非難し、8番陪審員にその理由を問いただす。
「わからない。有罪かもしれない。しかし、11人が有罪だ。私が賛成したら、かんたんに死刑になる。少年はまだ18歳だ。私が言いたいのは、たった5分で1人の少年の命を死刑と決めてしまって、もし間違いだったら・・・。1時間かけて話し合ってもいいじゃないか。どうせ、君が見たいナイターゲームは8時からなんだから」。

8番陪審員は、さらに続けて、
「考えてみてくれ。この少年はスラムで生まれ育ったんだ。母親は9歳のときに死に、父親が服役中は1年半を施設で過ごした。不幸な少年だった。反抗的な少年になったのも、毎日1回誰かに頭を殴られたからだ。惨めな人生だった。少年のために、少しは討論してやろう」。
話し合いが始める。まずは、有罪だと判断している11人の陪審員がそれぞれの有罪だと判断した理由を述べていく。中には、スラム街育ちはウソつきだから、有罪に決まっているというような言い方をする者もいる。それに対して、スラム街育ちだった他の陪審員は「それは偏見だ」と抗議する場面もある。
以上の話を聞いたうえで、8番陪審員は、「少年が殺人を犯したという根拠は、殺人そのものを見たという近所の女性の証言と、犯行時刻にあったとされる少年の「殺すぞ」という叫び声を聞き、現場から逃走する少年の姿を見たという階下に住む老人の目撃証言だが」・・・と前置きした上で、「あなたに質問がある。あなたは少年の証言は信じないくせに、なぜ女性らの証言は信じるんだ?間違いはないと言い切れるのか」。
次に、凶器とされるナイフについて陪審室に提出され、別の陪審員が凶器であるナイフについて説明しだす。「こんなめずらしいナイフ、私は見たことない!少年はナイフをなくしたというが、そのナイフと同じものが父親の胸に刺さっていた。こんな偶然があるもんか!」
8番「偶然じゃない、他に似たようなナイフがなかったかどうか、可能性を言ってるんだ!」
他の陪審員が「そんな可能性はないね!」
突然椅子から立ち上がりながら、8番はポケットに手をいれナイフを取り出した。そのナイフを、犯罪に使われたナイフの横に突きたてたのだ。テーブルに突き立てられたナイフは、犯行に使われたものと全く同じものだった。驚き騒ぐ11人の陪審員たち。

「これをどこで手に入れたんだ!?」
8番「昨夜、少年の近所を散歩したんだ。少年宅近所にある質屋でこれを購入した。たったの6ドルでね」
「同じナイフが10丁あったとしても彼が無実だという証明にはならんぞ」
「わかってる。でも可能性はあるじゃないか!」
有罪を主張している別の陪審員が言った。
「いったいどうなっているんだ! 目撃者がいて、少年が父親を刺したと証言してるんだ。ほかにどんな証拠が必要だ?」
再度の評決を実施する。すると、さらにひとり無罪の投票をする人が現れた。
無罪に回った理由について、「この方は1人で反対を主張された。無罪とはいわず確信がないと言った。11人も相手に1人で反対している。勇気ある発言だ。そして、だれかの支持にかけた。だから、私は応じた。少年はたぶん有罪だろうけれど、もう少し話を聞いてみたい」

審議が再開したものの、退屈して、メモ用紙の上でゲームをして遊びだす者が現れる。8番は、「遊んでいるばあいじゃないだろう」と怒って、そのメモ用紙を奪う。

階下に住む老人の証言の信憑性について議論が始まる。「殺すぞ」という少年の叫び声は、電車の通過時間帯だった。果たして、その時間に少年の叫び声やその内容まで聞き取れるのかが問題だった。塗装工である別の陪審員が、その付近で3日間作業をしたことがあり、電車が通過するとものすごい騒音になるため、「聞き取れないはずだ」と推測する。

階下に住む老人の走り去る少年を見たという目撃証言も、老人の住む部屋の間取りや老人が足が不自由なことから目撃は不可能ではないかという疑いが出てくる。

いちばん強行に有罪を主張していた3番陪審員が怒りだす。
「みんなで正義の裁きを与えようと集まったのに、8番のおとぎばなしを聞いたとたん、涙もろい腰抜けになりやがって。有罪に決まっている。電気椅子に早く送るべきだ」とわめきだす。
それにたいして、8番は、「あんたは死刑執行人か」と批判する。

「そうだ。その1人だ」。
「スイッチを押すつもりか」。
「ああ、押してやる」。
「社会の復讐者を気取っているのか。個人的な憎しみで殺したいのか。このサディストめが」。

サディストと言われた3番が、「殺してやる」と、怒りだす。

この騒動をうけて、別の陪審員が話し出す。
「こんな争いをやるために集まったのではない。われわれには責任がある。これが実は民主主義のすばらしいところだ。郵便で通告をうけるとみんながここへ集まってきて、まったく知らない人間の有罪・無罪を決める。この評決でわたしたちには損も得もしない。この国が強い理由はここにある」。

次に、ナイフの使い方について議論になる。その再現を試みる。目撃者である女性の証言では腕を振り下ろして殺害したとされている。つまり、ナイフの方向は下向きなはずだ。しかし、かつてスラム街に住んでいた陪審員は、ナイフの使い方はそうではないと解説する。そのナイフでは上向きになるはずだというのだ。

評決になる。今度は、有罪が3人。無罪が9人になる。それに怒りだした10番陪審員が、「スラムに住む人間はウソツキだ、殺人だって平気でやる連中だ」と、差別丸出しの発言をする。それに怒った他の陪審員がいっせいに背を向ける。

8番陪審員がポツリと語り始める。
「個人的な偏見を排除するのはいつも難しい。しかも、偏見は真実を曇らせる。私は真実を知らないし、だれにもわかるまい。9人は被告人を無罪だと思っている。でもこれは推理で間違いかもしれない。犯罪者を逃がすのかもしれない。まったくわからない。でも、筋の通った疑問がある。そこが肝心なところで、疑問があるかぎり有罪にできない。われわれ9人は理解できない。3人がなぜ有罪を確信するのかを」。
最終的には、殺人を目撃したという女性証言についてその信憑性が疑われることになるのだが、最後まで書いてしまうと、完璧なネタばれになってしまう。「12人の怒れる男」を観ていただければいい。陪審員がどういうことを期待され、どういうことをやったらいけないのかがそこには描きこまれている。
たとえば、ある裁判員裁判で裁判員を務めた方の以下のコメントと比較してみたらいいと思う。
証人の記憶はあいまいで、「何が本当なのか判断が難しかった」「その分、自分の感覚を大事に(推論を重ねて)意見を出した」。
「何が本当なのか判断が難しかった」のなら、「そこが肝心なところで、疑問があるかぎり有罪にできない」はずなのに、自分の感覚を大事にし推論を重ねて有罪にしてしまった。有罪の証拠が不十分ということで「疑わしきは罰せず」を持ち出すまでもなく、私なら無罪である。
日本の裁判員裁判はこんなていどなのだから、これから裁判員になる人は、どんな啓蒙書を繰り返し読むよりも、この映画を繰り返し観たほうが私はいいと思う。ぜひ、この機会に、全編をみていただきたい。
裁判員に求められること
さて、このようにして、8番陪審員の孤軍奮闘から始まって、最終的には少年は無罪を勝ち取るわけだが、市民参加の象徴的場面が最後に映像化されている。
裁判所を出て、そのときになって初めて、お互いの名前を交換するのだ。お互い名前を名乗ってそれで別れる。そして、陪審員はそれぞれの家庭や職場に復帰する。


ここに、市民が裁判に参加することの重要性が凝縮されているように私には思われる。ある陪審員が言っているように、
私たちが生きる現代社会、現代国家は、みんなが働いて日々の暮らしを立てるとともに、社会、国家を形成、維持している。ある人は大工さんとして生計を立て、ある人は農民として田んぼを耕し、生計を立てる。ある人は、工場で働いて、製品を作り、それで生計を立てる。ある人は、食事や洗濯、掃除をして、生計をしやすいようにするための技能を発揮する。ある人は、教師として生徒に教えることによって生計を立てる・・・。
みんながそれぞれに職業を持ち、そこで技能を発揮して生計を立てている。そして社会をまわしている。大工さんも農民も工場労働者も主婦も教師もそれぞれ職業を持ち、技能を発揮する。陪審制や裁判員裁判は、そういった職能を持った人たちが集まって、その職能だけでは解決できない問題を、名前も知らない者同士が、お互いの経験、知恵を出しあって解決しようとするものだ。そのときは、1個の職能人ではない。自分の職能の範囲内では解決できないことを、みんなが経験、知恵を出しあって、解決する。そのときは、職能人を離れて、一個の市民として立ち上がる。そして、職能人である裁判官や検察官=裁判の権力性に対する一つの対向原理をうち立てる。それが市民に期待され、課せられた責任である――と私は考える。
もっと具体的に言うなら、職能人である裁判官や検察官は、職能、つまり仕事として「裁判をする側」として日々裁判にかかわっている。どんなに重大な事件であったとしても、職能人としての裁判官や検察官にとっては、それはたくさん抱えた案件の中の一つにすぎない。そして、日々その案件の処理に追われている。多くの案件を抱えているから、どうしても効率的に処理しようということになりやすい。そうならざるをえない。そのため、個々の案件、事件の被告人の顔が見えなくなりがちだ。
しかし、陪審員や裁判員は違う。一生のうちに一回あるかないかで陪審員や裁判員に任命される。陪審員や裁判員にとって、自分が担当した事件は一生のうちの一回かぎりのものだ。陪審員および裁判員に期待されるのは、数ある事件のひとつとして処理するのではなく、その一回かぎりの事件に対して、被告人の実像に肉薄することである。陪審員(裁判員)はそのときは「裁判をする側」にあるが、同時に、市民としてはふだんは「裁判をされる側」にある。市民は、被告人と同じく「裁判をされる側」の立ち位置にもあるのだといえる。被告人に同情しろとか、肩を持てと言っているのではない。同じ「裁判をされる側」として、被告人の実像に迫るよう期待されている。それが陪審員や裁判員の責任なのだ。
陪審員(裁判員)にもうひとつ期待されていることがある。組織としての面子、しがらみから解放されていることである。名もなき市民が個々に裁判の時だけ集まってきて、自分の利害関係のない裁判にかかわる。そして、同じ市民であるまったく知らない人間の有罪・無罪を決める。職能人だけで構成された社会は、その職能社会という組織に埋没してしまって、個がなく、個人に備わっている想像力を奪われてしまう。だから、被告人の実像に迫れない。検察の組織防衛とか面子とかがそうだ。裁判所内のヒエラルキーによる個々の裁判官の自己保身もありえるだろう。だからこそ、そのような職能社会からは解決しがたい問題について、市民として参加する。そういうものとして、市民は期待されているのだと、私は思う。そこに市民としての責任があるのだと、私は考える。
われわれはひとりひとり例外になる
さて、そこでだ。あなたはヘンリーフォンダ演じる8番陪審員になれるだろうか。そこには、事実を丹念に吟味する探究心と、「われわれはひとりひとり例外になる。孤立する。例外でありつづけ、悩み、敗北を覚悟して戦いつづけること」(辺見庸の言葉)という信念がある。
丸山真男は、デモクラシーの精神構造として何が大切かについて、以下のように述べている。
[amazonjs asin=”4622036592″ locale=”JP” title=”自己内対話―3冊のノートから”]まず人間ひとりひとりが独立の人間になること。真偽、正邪を自らの判断において下す。
↓
他人のつくった型に入りこむのでなく、自分で自分の思考の型をつくって行くこと。間違っていると思うことには、まっすぐにノーということ。この「ノー」といいうる精神―――孟子の千万人といえども我行かんという精神―――は就中重要である。このノーといえない性格の弱さ(注)が、雷同、面従腹背、党派性、仲介者を立てたがる事、妥協性等々もろもろの国民的欠缺のもと。(注)独立的精神の苦しさに堪えられない、弱さ。自主的思索を放棄して、他人のつくった枠に入り込むことは最も安易である。
(「自己内対話」P10-)