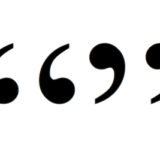ある掲示板を拝見して
以前、ときどき訪問し、何度か書き込んでもいたサイトの掲示板にしばらくぶりで訪問した。掲示板には、交通事故被害者の方が人身傷害保険による後遺障害をふくめた支払予定明細を書き込んでいて、その額が妥当かどうか質問されていた。その中から一部引用すると、
>労働能力喪失率5%。労働能力喪失期間2年。
それに対して常連の回答者の方が、
>加入保険会社との交渉により、保険金額の増額を目指しておられるのだとしたら、そちらの方向性に見込みはないものとお考え下さい。人身傷害保険では、その金額が適正かどうかではなく、事前契約によって決められた金額が支払われるのが原則だからです。
約款にすべてが書いてあるわけではない
原則論としては正しいのかもしれないが、約款で一から十まで何でも決められているわけではないし、解釈の余地がある規定も存在する。しかし、相談者はこの回答を真に受けて示談してしまったようであり、もう後の祭り、It’s Too Late、もう手遅れなので、私がいまさら書き込みをするのもどうかと思ったから、こちらに書くことにした。
人身傷害保険とは
人身傷害補償保険とは、人身に関する損害について、加入の任意保険会社から、約款に従った保険金の支払を受けることができる保険である。治療費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、交通費、休業損害など一般的な損害項目に関して補償を受けることができる。支払い基準が約款で明確化されているものが多いことから、金額に関して争えないことが多いのも事実である。
たとえば労働能力喪失期間について
とはいえ、人身傷害保険の約款になんでもかんでもすべて、一から十まで記載されているわけではない。たとえば労働能力喪失期間についてである。相談者への提示は2年である。しかし、約款にそのように明記されているわけではない。約款には「「障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案して決定する」とあるだけだろう。
むち打ち症による後遺障害14級の場合のこの2年がはたしてどこまで妥当だろうか。裁判基準なら2年から5年だと言われているため(注1)、2年が不当とまでは言えないと言われているが、やはり短いなあと思わざるえない。5年はさすがに保険会社も認めないだろうから示談では無理だろうし、裁判で争うしかないが、残存症状しだいでは3年くらいなら交渉の余地があったかもしれない。2年と3年とでどれくらい違うか。わずか1年の違いだが、もとが2年なのでかなりの額の開きがあるはずだ。
「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」
「交通賠償論の新次元」
「交通事故におけるむち打ち損傷問題」
労働能力喪失期間2年は6%の真実
2年というのは不当でないといわれているけれど、裁判例のわずか6%である。他方、5年以上は58%である。「以上」とある中には就労可能年齢である67歳まで認めた裁判例も存在する。損保の提示は、やはりどう考えても短いと思わざる得ない。保険会社はあえて短く労働喪失期間を2年とした自分に都合のいい判例をもとに算定しているといわれてもしようがないんじゃないだろうか。
労働能力喪失率も気になるところ
このように、人身傷害保険は契約で決まるものであり、その契約内容も約款で仔細について取り決めている。だから、提示された保険金額は争えないのだとよく言われる。ふつうはそうなのだろうけれど、そこで納得してしまって思考停止したらだめだと思う。支払明細の根拠を約款にどう書いてあるのかいちど当たってみること。それが大切だと思う。
労働能力喪失期間以外に、労働能力喪失率も気になるところだ。後遺障害に該当する傷病の中には、たとえば歯の欠損障害とか、醜状障害とか、ある種の変形障害とかなどが労働能力喪失率に影響を及ぼさないとも言われている。人身傷害保険でこれらの傷病がどのように扱われているのか私は知らないのだが、いちおうの注意が必要だと思う。